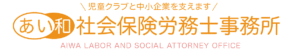2026(令和8)年4月に小学1年生となるおこさんがいるご家庭へ。放課後児童クラブ(学童保育所)入所手続きを確認しましょう。第2弾。
放課後児童クラブ(いわゆる学童保育所)運営者をサポートする「運営支援」を行っている「あい和学童クラブ運営法人」代表の萩原和也です。放課後児童クラブを舞台に、新人職員の苦闘と成長、保護者の子育ての現実を描く、成長ストーリーであり人間ドラマ小説「がくどう、 序」が、アマゾン (https://amzn.asia/d/3r2KIzc)で発売中です。ぜひ手に取ってみてください! お読みいただけたら、アマゾンの販売ページに星を付けていただけますでしょうか。そして感想をネットやSNSに投稿してください! 最終目標は映像化です。学童の世界をもっと世間に知らせたい、それだけが願いです。ぜひドラマ、映画、漫画にしてください!
2025年8月18日付の運営支援ブログで、そろそろ来年度(2026年、令和8年)の児童クラブ入所手続きの案内をしている自治体が出てきましたよ、来年は児童クラブを利用したいと考えている子育て世帯の方は、お住いの自治体が出す児童クラブの入所案内情報をチェックしましょうね、と呼びかけました。今回はその第2弾。9月も半ばに入るので、前回よりは来年度の入所に関して案内をしている自治体は増えているようですよ。児童クラブの入所手続きを忘れてしまった、入所手続きの必要性を知らなかった、そのために児童クラブに4月から入れなかったという悲劇をゼロにしたいのです。なお、10月にもなるとほとんどの自治体で新規入所の案内をしますから、基本的にこの第2弾でおしまいデス。
(※基本的に運営支援ブログでは、学童保育所について「放課後児童クラブ」(略して児童クラブ、クラブ)と記載しています。放課後児童クラブはおおむね学童保育所と同じです。)
※児童クラブの入所に関する情報は必ずご自身が、お住まいの地域の自治体や、児童クラブ運営事業者に個別に確認してください。この運営支援ブログの情報を基にして判断しないでください。この運営支援ブログに掲載しているのは引用であり、二次情報です。常に一次情報=一番最初に発信された情報=を入手して、判断してください。
<来年度の児童クラブ入所の案内が続々と登場>
前回と同じく、検索には、「楽天ウェブ検索」「グーグル」を使用します。検索ワードは「学童保育所 放課後児童クラブ 令和8年 2026年 入所 申請 利用」です。検索の結果、表示されたウェブのページの文言で、手続き等の時期に関する情報が含まれているものを紹介します。ちなみに前回の投稿ですでに来年度の児童クラブ入所案内をホームページに載せていたのは「東京都八王子市(子育て応援サイト)」、「埼玉県ふじみ野市」(ここまで楽天ウェブ検索)、「東京都文京区」、またグーグルニュース検索では「静岡県森町」、「東京都国分寺市」、「兵庫県三田市」、「神奈川県横須賀市」がありました。
今回はどうでしょう。楽天とグーグルで同じように検索して、すぐにヒットした自治体を紹介します。
北日本にあたる地域から順に掲載していきます。
「山形県上山市」は「令和8年度放課後児童クラブ(学童保育)申込み受付について」と題したページを公開しています。
「群馬県伊勢崎市」は「令和8年度 放課後児童クラブへの入所案内(一斉入所)」と題したページを公開しています。
「群馬県みどり市」は「令和8年度の学童保育所の入所児童を募集」と題したページを公開しています。
「茨城県神栖市」は「2026年度放課後児童クラブ利用者募集(一斉募集)」と題したページを公開しています。西暦表示ですね!
「埼玉県狭山市」は「令和8年度公立学童保育室の申込み」と題したページを公開しています。
「埼玉県桶川市」は「令和8年度4月放課後児童クラブの申し込みについて【受付期間10/15~】」と題したページを公開しています。
「埼玉県志木市」は「保育園・学童保育クラブ令和8年4月からの新規入園・入所のお知らせ」と題したページを公開しています。
「東京都日野市」は「令和8年度 学童クラブ入所申請について」と題したページを公開しています。
「長野県安曇野市」は「令和8年度児童クラブ入所申請について」と題したページを公開しています。
「静岡県袋井市」は「令和8年度放課後児童クラブ入所申込受付について」と題したページを公開しています。
「福井県小浜市」は「令和8年度放課後児童クラブ会員を募集します」と題したページを公開しています。
「愛知県碧南市」は、放課後児童クラブの情報公開ページの中に「令和8年度 放課後児童クラブ通所について」という記事を掲載しています。
「愛知県蒲郡市」は、児童クラブのページの中に「令和8年度 児童クラブ入所申込」の記事を掲載しています。
「愛知県岩倉市」は、「放課後児童クラブ(通年での入所)の申込について」と題したページの中に、「令和8年度の申込(一斉申込)について」の記事を掲載しています。すでに受付中です。
「三重県伊勢市」は「令和8年度放課後児童クラブの利用児童募集について」と題したページを公開しています。
「滋賀県近江八幡市」は、市のホームページからダウンロードできる「放課後児童クラブ紹介のしおり」の内容を更新して令和8年度入所の説明会の日程を記載しているとのことです。
「滋賀県草津市」は「令和8年度 児童育成クラブ新規入会申請について」と題したページを公開しています。
「滋賀県湖南市」は「【令和8年度】学童保育所入所者募集について」と題したページを公開しています。
「奈良県葛城市」は「令和8年度 学童保育所入所者募集について」と題したページを公開しています。
「大阪府箕面市」は、放課後児童クラブの情報公開ページの中に「令和8年度(2026年度)学童保育利用申込の受付を開始します」という記事を掲載しています。
「兵庫県三田市」にお住いの子育て世帯は要注意です。三田市は「令和8年度から放課後児童クラブ入所申請受付期間が変わります。」と題したページを公開しています。
「岡山県瀬戸内市」は「令和8年度放課後児童クラブ入所受付について」と題したページを公開しています。
「沖縄県読谷村」は「令和8年度公立放課後児童クラブ入所申込について」と題したページを公開しています。
「沖縄県宜野湾市」は「令和8年度 宜野湾市公立放課後児童クラブ4月1日入所申込のお知らせ」と題したページを公開しています。
<必ず定期的に確認を!>
2026年、令和8年の4月から、おこさんを放課後児童クラブ(学童保育所)に入所させたいと考えている保護者さんは、「のんびり」しないでください。もうすでに、あちこちの自治体で来年度の入所に関する情報を提供したり、早い地域ではすでに申し込みを受け付けています。必ず、入所に関する情報を、「自分からゲット」するようにしましょう。
児童クラブの呼び方は地域ごとに違います。児童クラブ、学童保育所、留守家庭児童室、学童クラブ、「~クラブ」とか、実に様々ですが、小学生のこどもを受け入れる施設が児童クラブ、学童保育所です。その入所に関する情報は、主に、次のようなところで確認できることが多いです。
・市区町村のホームページ
・市区町村が配布する「広報紙」
・新1年生のこどもの場合、入学する予定の学校で行われる「就学児検診」の際の説明の時間
・通っている保育所や保育園、幼稚園、認定こども園などの「掲示物」
・住んでいる地域の市役所庁舎や町役場、村役場の庁舎や、支所にある掲示板や、配布物を置いている棚、ラック
・地域にある児童クラブ、学童クラブ、学童保育所にも、入所案内を備えているところがあります。
児童クラブに入所する、入所しないは、あくまで保護者の判断です。そういう「任意」の事柄については、市区町村も児童クラブの事業所も、あくまで「受け身」の姿勢なんですね。それが現実です。つまり、「児童クラブを利用しようかな、どうしようかな」という人が、自ら、自分の意志で、「情報を入手する行動をする」ことが大事です。何もしないでいて、役所や児童クラブから情報が送り届けられることは、まずありません。
いいですか、とても大事ですから何度でも書きます。「来年、2026年、令和8年の4月から、こどもを児童クラブ、学童保育所に通わせたいと、少しでも思っているなら、まずは情報をキャッチしましょう。役所のホームページを見る、広報紙を見てみる、通っている保育所やこども園、幼稚園の掲示板を見るなどして、自分から情報を手に入れよう」
ホームページは一番手っ取り早い確認方法です。検索で、住んでいる地域の自治体の名前と、「児童クラブ 学童保育所 2026年 令和8年 入所 案内」とでも検索ワードを入れて検索してみましょう。ただ、すべての自治体が、すみやかに新規入所の情報を掲載するかといえば、そんなことはありません。9月の終わりごろになっても、自治体のホームページに児童クラブ、学童保育所の新規入所の情報が掲載されていない場合は、住んでいる地域の市役所や町役場、村役場、区役所に、電話で問い合わせてみてください。自治体、とくに町村によってはホームページに情報を掲載しないところが、あるかもしれません。ホームページに必ず掲載されるとは、思わないでください。
いわゆる「民間学童保育所」という施設の場合は、市区町村のホームページに入所に関する情報は、まず掲載されません。なぜなら民間学童保育所というのは、公の事業である「放課後児童健全育成事業」ではないことがほとんどで、市区町村の管理下ではないからです。この場合は、その民間学童保育所のホームページや運営会社に問い合わせることが必要です。
つまり、一般的な「児童クラブ」「学童保育所」の場合(=公の事業としての、放課後児童健全育成事業を行っている施設や会社、団体)は、自治体のホームページに情報が掲載されることが多いですが、絶対ではないので、情報が見つからない場合は、すぐに、自治体に問い合わせてください。まして、小さな町村ではホームページに情報が掲載されない場合もあります。ホームページに情報が掲載されたことに気づいたとしても、入所締め切り期限まであと数日! ということになるかもしれません。できる限り、何度も繰り返し、情報をつかむように、頑張りましょう。
また、都市部や人口が多い地域において、英語やスポーツ、プログラム、学力アップをPRしている施設は「民間学童保育所」の可能性が高いので、そういう施設の入所に関する情報は自治体の掲載されないことがほとんどですから、直接、その施設や運営会社に問い合わせましょう。
<なぜこんなにしつこく書くのか>
それはですね、「すべての人が、当たり前に、情報をキャッチできる、情報を調べようとするのではないから」ということです。「いやいや、普通の人なら、児童クラブに入所させなきゃと考えれば自分で情報を探すでしょうに」と多くの人が思うかもしれません。
違います。そんなことはありません。こどもを児童クラブに入れないと来年4月から仕事と育児の両立ができないということが「予想できない」人は、絶対にいます。世の中の多くの人が言う「普通」は、世の中のすべての人にとって「普通」ではないのです。
振込詐欺に騙される人が今なお多数に及んでいる、ひどい状況を考えてください。「普通」、警察官や検察官を名乗る人が個人のスマホや自宅の固定電話に電話をかけてきて「あなた、逮捕されますよ。逮捕されないようにするにはお金を指定の口座に振り込んでください」と言われて、「そんなバカげた手口に騙されるわけないでしょう。逮捕したい人に向かって、あなた逮捕されますよと告げる捜査機関があるはずがない。みすみす逃げられてしまうではないか」と多くの人が思うでしょう。でも、現実は「普通なら騙されない」という手口に、騙されてしまう人が多いのです。
今の時点でこどもが保育所やこども園に通っていて、来年にそのこどもが新1年生になる、そういう子を育てている保護者であれば「普通」、来年以降は児童クラブ、学童保育所を利用するだろうと、多くの人が考える。考えるのは事実でしょう。でも、中には、「そうか、児童クラブに申し込まなきゃ」と思わない人だって、いるんですよ。こういう人に私は実際、何人もお会いしています。「小学校は特に手続きをしないでも入学できるから、学童保育所も、同じかと思った。保育所から情報が引き継がれて学童に入れると思っていました」
市区町村の児童クラブ担当者の方や、児童クラブを運営している事業者のみなさんへ、運営支援から心を込めてお願いします。「普通なら」分かるであろうということは決して思わないでください。4月になって、途方に暮れる保護者を、まして、4月から、安全安心な居場所が用意されないこどもを1人でも増やしたくないのです。ですから、担当者の方や事業者の方は、何度でも何度でも、多彩な手段手法で、「児童クラブが必要な人は、必ず手続きをしてください。必要かどうかわからない人は、相談してください」ということを周知してください。
例えば、窓口に入所申請に来た人に、こう告げてください。「もし周りに、同じように働きながら、あるいは学校に通ったり誰かを介護看病していたりしながらこどもを育てている人がいたら、その人たちにもれなく、児童クラブはどうするの? 手続きはしたの? 相談はした?、と声をかけてください。1人でも、居場所を見つけられずに困ったことになるこどもがいないようにしたいんですよ」
「そんなこといっても、ここは待機児童が出ている地域だからね。児童クラブに入れない、入らないこどもがいればそれだけうちのこどもが入所できる確率が高まるから」などとは思わないでください。その待機児童に対する不満や恨みはぜひ、住んでいる地域の市区町村に、思う存分にぶつけてください。同じように子育てしている方を追いつめたり悩ませたりしないように、そこはぜひ、ご理解をよろしくお願いします。
<運営支援の希望>
児童クラブは基本的に「単年度」つまりその年度だけの事業です。毎年毎年、新規入所児童を受け入れるのは当然として、すでに入所しているこどもについても「継続申請」「継続入所の手続き」が必要となることが圧倒的に多い状況です。
事業としては、予算は単年度ですから年度ごとの事業であるので、児童クラブに在籍しているこどもについても年度ごとに新たに入所要件を確認するというのは、そりゃ理屈は成り立つでしょう。
しかし運営支援は、あえて希望をぶち上げます。「継続入所の場合は、ごく簡単な手続き、例えば紙ぺら1枚の継続希望申請だけでいいじゃないか。何度も就労証明書とか、在学証明書とか、そういう手続きを保護者に求めるのは、もう取りやめましょうよ」と。
児童クラブの入所の要件に「留守家庭」であること、という要件がほぼすべての自治体で設けられているので、保護者の就労証明書などが、毎年度、必要としているという理屈ですが、運営支援はその点について、「保護者が以前に提出した就労証明書に記載されている内容と変化があった場合は、すみやかに再提出することを徹底し、年度替わりでの機械的な再提出は不要」とすることを主張します。転職して勤務先が変わったとか、人事異動で勤務する会社は同じでも勤務場所が変わったとか、以前に提出した内容と変化があったときだけ就労証明書の提出を求めることとし、ただし、内容が変化したのに再提出を怠った場合は退所、退会処分もありえる、とその点は厳格化することで、運営支援は良いのではないかと訴えます。
非正規雇用の場合は就業先を転々とすることがあるでしょうが、それは緊急時の連絡先を児童クラブ側が把握するために必要ですし、あるいは利用料や保護者負担金の請求の際の連絡先としても知っておきたいので、就業先を変える都度、やはり就労証明書の提出は必要でしょう。派遣労働者の場合、就業先は変わりますが派遣元において雇用されているのですから派遣元が変わらなければ就業先が変わっても(新たな勤務先、就業先についての連絡先は別途の用紙で事業者や児童クラブ職員に伝えることは絶対に必要ですが)就労証明書の提出まで求めなくてもよいと、運営支援は考えます。
自治体の条例や管理規則、要綱において、就労証明書などは毎年確認するとあっても、それは自治体だけで変えられるものですからね。
運営側も保護者側も、お互いに事務作業や手続きに要する手間ひまが減って楽になりますよ。費用も少しは減りますよ。必要な時間も減りますよね。そんなことはなるべく削減していきましょうよ。
(お知らせ)
<社会保険労務士事務所を開設しました!>
2025年9月1日付で、わたくし萩原が社会保険労務士となり、同日に「あい和社会保険労務士事務所」を開業しました。放課後児童クラブ(学童保育所)を中心に中小企業の労務サポートを主に手掛けて参ります。なお、放課後児童クラブ(学童保育所)に関して、労働関係の法令や労務管理に関すること、事業に関わるリスクマネジメント、生産性向上に関すること、そしていわゆる日本版DBS制度に関しては、「あい和社会保険労務士事務所」を窓口にして相談や業務の依頼をお受けいたします。「あい和社会保険労務士事務所」HP(https://aiwagakudou.com/aiwa-sr-office/)内の「問い合わせフォーム」から、ご連絡のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
「一般社団法人あい和学童クラブ運営法人」は、引き続き、放課後児童クラブ(学童保育所)の一般的なお困りごとや相談ごとを承ります。児童クラブの有識者として相談したいこと、話を聞いてほしいことがございましたら、「あい和学童クラブ運営法人」の問い合わせフォームからご連絡ください。子育て支援と児童クラブ・学童保育の運営者の方、そして行政の子育て支援と児童クラブ・学童保育担当者の方、議員の方々、ぜひとも子どもたちの安全と安心を守る場所づくりのために、一緒に考えていきましょう。セミナー、勉強会の講師にぜひお声がけください。個別の事業者運営の支援、フォローも可能です、ぜひご相談ください。
☆
(ここまで、このブログをお読みいただきありがとうございました。少しでも共感できる部分がありましたら、ツイッターで萩原和也のフォローをお願いします。フェイスブックのあい和学童クラブ運営法人のページのフォロワーになっていただけますと、この上ない幸いです。よろしくお願いいたします。ご意見ご感想も、お問合せフォームからお寄せください。出典が明記されていれば引用は自由になさってください。)