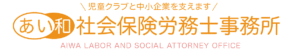高市内閣が発足しました。新内閣と、黄川田仁志・こども政策担当大臣には放課後児童クラブ(学童保育所)の充実を!
放課後児童クラブ(いわゆる学童保育所)運営者と働く職員をサポートする「あい和学童クラブ運営法人」代表の萩原和也です。放課後児童クラブを舞台にした人間ドラマ小説「がくどう、 序」が、アマゾン (https://amzn.asia/d/3r2KIzc)で発売中です。ぜひ手に取ってみてください! 「ただ、こどもが好き」だからと児童クラブに就職した新人職員の苦闘と成長、保護者の子育ての現実を描く成長ストーリーです。お読みいただけたら、アマゾンの販売ページに星を付けていただけますでしょうか。そして感想をネットやSNSに投稿してください! 最終目標は映像化です。学童の世界をもっと世間に知らせたい、それだけが願いです。ぜひドラマ、映画、漫画にしてください!
高市早苗自民党総裁が2025年10月21日、第104代内閣総理大臣に選出され、高市内閣が発足しました。介護報酬の見直しに積極的であるとして介護業界の期待は相当高まっているようです。放課後児童クラブについてもぜひ、黄川田仁志こども政策担当大臣との師弟コンビ(松下政経塾つながり)で、後世に「さすが!」と感激される抜本的改革に取り組んでいただけるよう、運営支援はご期待申し上げます。
(※基本的に運営支援ブログと社労士ブログでは、学童保育所について「放課後児童クラブ」(略して児童クラブ、クラブ)と記載しています。放課後児童クラブは、いわゆる学童保育所と、おおむね同じです。)
<ぜひ取り組んでいただきたいこと>
僭越ながらわたくし萩原から高市内閣、黄川田大臣に、放課後児童クラブに関して、「ぜひ取り組んでいただきたいこと」を紹介申し上げます。これらに着手することで、放課後児童クラブが安定して持続的に事業を営むことが容易となり、子育て世帯のワークライフバランスが安定します。なにより、こどもにとって質の高い育ちの保障が確保できることはこどもの利益になります。保護者も安定して社会経済活動に関われることができますし、またそれぞれにキャリアの充実に取り組めることで、社会が安定します。労働力不足が著しい日本の労働経済の拡大に貢献します。
その1「放課後児童クラブの量的整備のさらなるスピードアップで、待機児童解消」
→放課後児童クラブを利用したいすべての子育て世帯が、児童クラブを利用できることは絶対的に優先度が最高位にあると運営支援は考えます。待機児童になったこどもは、安全安心な居場所を社会が保障できません。保護者はこどもの監護のために今までの職を捨てたり替えたりすることを余儀なくされ、キャリアの断絶を招きます。しかもだいたいにおいて、不利益をこうむるのは女性(母親)です。世帯収入の減少をも伴います。児童クラブの待機児童は、何一つ良いことがありません。
待機児童を生じさせないために、基礎自治体が児童クラブのための予算を確保しやすくなるように、期間限定でもいいので、運営費における国の負担割合(現在は全体の6分の1)を大幅に引き上げることと、児童クラブを民間が新設する際の補助金の創設が必要です。現在は既存の建物の改修について補助が出ていますが、新設についても補助を出すべきでしょう。その際は、仮に少子化の影響で児童クラブとしての事業継続が困難となった場合は、他の児童福祉事業等への転用を認めることで補助金の返還などを免除する制度も必要でしょう。民間企業の事業意欲をうまく利用することが必要です。
その2「放課後児童クラブの事業の質の向上」
→待機児童解消は喫緊の課題ですが、待機児童を解消しさえすれば良いものではありません。また、いわゆる「放課後全児童対策事業」(午後5時までは文部科学省の「放課後子供教室」、それ以降はこども家庭庁の「放課後児童健全育成事業」を同じ場所で同じ職員によって実施する市町村の独自事業)によって待機児童が生じていない地域も大都市を中心にかなりの地域に及んでいます。それらの地域では待機児童問題こそありませんが、深刻な「大規模状態」の影響で、こどもたちの過ごす環境の悪化と、職員の職場環境の悪化による看過できない問題が生じています。朝夕の通勤電車内のラッシュ状態が児童クラブの中で常時、発生していると想像してください。月曜日から金曜日までずっと、そんなギュウギュウ詰めの環境で数時間を過ごすこどもたちのメンタル面が良好でいられるはずがありません。こどもたちは疲弊し、他児とのいさかい、トラブルが多発し、その対応に職員がエンドレスで追われることになります。あまりにも大勢のこどもたちの声で、職員たちは相次いで突発性難聴になります。職員は疲弊し、低賃金重労働があいまって、すぐに辞めてしまいます。大規模状態の児童クラブは、何一つ、良いことがありません。
そんな劣悪な児童クラブの環境でこども時代を過ごすこどもたちが、高市首相や黄川田大臣が愛するこの日本国のことが好きになれますか? 生まれ育った故郷に良いイメージを持てますか? 社会を動かす大人たち、政治家たちを信頼できるようになりますか? それを思えば、児童クラブの抜本的な拡充こそ必要だとお分かりになることと運営支援は期待します。
その3「放課後児童クラブの制度設計の見直し」
→保育所と同じ「児童福祉施設」と位置付けるべきです。現在の放課後児童クラブは「放課後児童健全育成事業」であって、「事業」です。児童福祉法による法定の事業ですが、市町村の任意の事業です。これを、小学生の子育てを支援するための児童福祉施設として再定義することが必要です。これによって、児童クラブを対象とした補助金を国がいろいろと用意しても市区町村の裁量で適用する、適用しないという地域格差は無くなります。それは児童クラブの運営を安定させ、地域社会の安定にも大いに資することになります。一部の財政事情が良好な基礎自治体が児童クラブの整備を進めることでそのような地域に人口が集中することを防ぐことで、地域の発展、国土の均一的な発展にも役立ちます。
その4「放課後児童という枠を取っ払い、子育てにおいて支援が必要な世帯のこどもを受け入れる施設とする」
→現行の放課後児童クラブは、「就労等によって」という保護者の事情があって監護ができないこどもを受け入れる事業として設計されています。現状は、保護者が働いていようがいまいが、就学していようがいまいが、看護や介護をしていようがいまいが、「保護者自身の子育てに関する気持ち、能力、技術」など種々の事情において子育てに悩み、苦しんでいる保護者が大勢います。その結果が児童虐待として表面化する不幸な事態をも招きます。かつての日本は、地域全体で、あるいは祖父母や親類の濃密な関わりによって子育てを血縁社会、地域社会全体で支えることができました。いまやもうそのような環境はほぼありません。子育ての悩みや戸惑いは「家庭」それも核家族化した少数の家族だけが抱える悩みや戸惑い、苦しみとなっています。家族は社会の基本ですが、その基本たる家族が子育ての悩みや苦しみを背負って過ごしています。その負担を、児童クラブが軽減することができます。解消に導くことができます。児童クラブの利用の要件に就労等、保護者が留守であることを撤廃し、「健全育成の支援を望む子育て世帯」に対象を広げて、子育て世帯が、こどもの健全育成の専門家が従事している児童クラブと共に子育てができるようにするべきです。
その5「補助金の適切な利用に目を光らせることで税金の効率的な使用を実現する」
→放課後児童クラブは民間事業者も実施することができると児童福祉法に定められています。それは児童クラブが自然発生的に民間から生まれた由来からすれば当然です。そして「子ども・子育て支援新制度」が第2次安部政権によって着実に履行され、同時に児童クラブへの補助金が増額されていく過程において、その補助金を巧妙に利益計上することで事業が成り立つ余地を生じさせました。民間企業が児童クラブ運営に乗り出すことは決して悪いことばかりではありませんし、評価できる点もあります。しかし残念ながら、現状においてまだまだ不十分である補助金をさらに巧妙にやりくりすることで、児童クラブを運営する民間事業者が、本来、放課後児童健全育成事業に投下されるべき予算(それは6~7割が補助金のことが多く、特別区でいえばさらにその割合が上昇)が投下されずに事業者の利益として計上されています。つまり、「児童クラブの運営のために交付した補助金の半額以上がそのまま事業者の純利益となってしまっている」状況が生じています。それが「補助金ビジネス」です。そのような事業者では、児童クラブの職員の賃金は最低賃金とほぼ同額であり、こどもが使う折り紙や読む本すら経費がないので購入できず、職員が自腹で購入したり保護者の寄付でまかなったりしています。補助金の効率的な使い方としてはありえません。効率的な使い方をされていれば、もっと多くの児童クラブが質の高い事業運営ができるはずです。この状況にメスを入れるべきです。手法はいくらでもあります。
その6「本当の、リアルな姿の児童クラブを視察してください」
→他にもいろいろありますが、高市総理、黄川田大臣にはぜひとも、リアルな児童クラブを目の当たりにしていただきたいと運営支援は切望します。直ちに、です。官邸やこども家庭庁からほど近い場所にある、おぜん立てされた整った児童クラブではなくて、ちょっと離れた地方の、公設クラブや公営クラブを、ありのままの状態で視察していただきたいのです。きっとそこには、大規模状態や、ボロボロの施設の児童クラブの実態があります。そもそも都内のクラブや、裕福な事業者が運営する児童クラブは、児童クラブの世界では例外的な世界のクラブです。そんなクラブを見ても、児童クラブの世界の真の姿はつかめません。なんなら私が案内します。安い給料で長時間、職員数が少ないが故の過重労働に苦しみながらも、あすを担うこどもたちと、こどもたちを育てる保護者のために「やりがい搾取」を受けながらも必死に働いている、職員たちがそこにはいます。ひどい環境でも我慢して過ごしているこどもたちがいます。予算を増やして状況を改善したくても先立つモノがないのでできない自治体の行政パーソンもいます。ぜひ、ごく一般的なありのままの児童クラブを視察してください。
<介護の世界は期待。ですから児童福祉の世界も!>
高市首相は就任後の会見で、物価高対策に取り組む意欲を語られました。その中で、これはご自身の体験にもよるのでしょうが、医療や介護の世界を苦しめている問題にも直ちに取り組むと表明されました。さっそく、業界の専門メディアが好意的に取り上げています。わたくしは、とてもうらやましいと思います。
例えば、介護の専門メディアである「JOINT 介護ニュース」は10月21日の配信記事で、以下のように記載しています。引用して紹介します。
「会見後に開く初閣議で物価高対策の取りまとめを指示すると明言。その中に医療・介護現場への支援策も盛り込む意向を示し、「診療報酬・介護報酬の改定時期を待たずに、病院や介護施設の経営改善、働いている方々の処遇改善につながる補助金を前倒しで措置する」と述べた。」
医療や介護の世界に従事すると思われる方々から、X(旧ツイッター)では歓迎するコメントが目立ちます。
これをぜひ、児童クラブでもやりましょう。やってください。そのために、先に掲げた6項目だけは直ちに着手していただきたい。時間がかかる内容もありますが、日本の未来を担うこどものために必要なことだと運営支援は考えます。ぜひとも取り組んでいただきたい。
黄川田大臣は専門が安全保障のようですね。政治と経済の安定は当然に安全保障政策の基本ですが、次代を担うこどもが健やかに成長しなければ社会の安定はありえません。また、黄川田大臣は埼玉3区が選挙区ですが、埼玉3区は越谷市の全域と川口市の一部が選挙区に含まれています。越谷市はまさに放課後児童クラブの待機児童数が大変多い地域です。令和6年の放課後児童クラブ実施状況では、越谷市は全国の児童クラブの待機児童数では最も多い395人となっています。大臣ですから日本全国あらゆる地域の児童クラブの現状の改善に勤しんでいただきたいのですが、こと、地盤、足元の選挙区の児童クラブ待機児童数が日本でワースト1の地域である気鋭の政治家が放課後児童クラブを所管する省庁のトップになったのも、何かの縁でしょう。越谷市の子育て世帯の人が安心してワークライフバランスに配慮した生活ができるよう、児童クラブの量と質の抜本的かつ即効性あるテコ入れを、黄川田大臣にはぜひとも期待いたします。
(お知らせ)
<社会保険労務士事務所を開設しました!>
2025年9月1日付で、わたくし萩原が社会保険労務士となり、同日に「あい和社会保険労務士事務所」を開業しました。放課後児童クラブ(学童保育所)を中心に中小企業の労務サポートを主に手掛けて参ります。なお、放課後児童クラブ(学童保育所)に関して、労働関係の法令や労務管理に関すること、事業に関わるリスクマネジメント、生産性向上に関すること、そしていわゆる日本版DBS制度に関しては、「あい和社会保険労務士事務所」を窓口にして相談や業務の依頼をお受けいたします。「あい和社会保険労務士事務所」HP(https://aiwagakudou.com/aiwa-sr-office/)内の「問い合わせフォーム」から、ご連絡のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
☆
「一般社団法人あい和学童クラブ運営法人」は、引き続き、放課後児童クラブ(学童保育所)の一般的なお困りごとや相談ごとを承ります。児童クラブの有識者として相談したいこと、話を聞いてほしいことがございましたら、「あい和学童クラブ運営法人」の問い合わせフォームからご連絡ください。子育て支援と児童クラブ・学童保育の運営者の方、そして行政の子育て支援と児童クラブ・学童保育担当者の方、議員の方々、ぜひとも子どもたちの安全と安心を守る場所づくりのために、一緒に考えていきましょう。セミナー、勉強会の講師にぜひお声がけください。個別の事業者運営の支援、フォローも可能です、ぜひご相談ください。
☆
(ここまで、このブログをお読みいただきありがとうございました。少しでも共感できる部分がありましたら、ツイッターで萩原和也のフォローをお願いします。フェイスブックのあい和学童クラブ運営法人のページのフォロワーになっていただけますと、この上ない幸いです。よろしくお願いいたします。ご意見ご感想も、お問合せフォームからお寄せください。出典が明記されていれば引用は自由になさってください。)