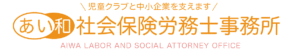社会やメディアに知ってほしい、放課後児童クラブ(学童保育所)の「ここを改善して!」の厳選10点を紹介します。
放課後児童クラブ(いわゆる学童保育所)運営者と働く職員をサポートする「あい和学童クラブ運営法人」代表の萩原和也です。放課後児童クラブを舞台にした人間ドラマ小説「がくどう、 序」が、アマゾン (https://amzn.asia/d/3r2KIzc)で発売中です。ぜひ手に取ってみてください! 「ただ、こどもが好き」だからと児童クラブに就職した新人職員の苦闘と成長、保護者の子育ての現実を描く成長ストーリーです。お読みいただけたら、アマゾンの販売ページに星を付けていただけますでしょうか。そして感想をネットやSNSに投稿してください! 最終目標は映像化です。学童の世界をもっと世間に知らせたい、それだけが願いです。ぜひドラマ、映画、漫画にしてください!
今回のブログは、放課後児童クラブの世界を大きく改善できる大事なポイントを運営支援の独断と偏見のもとに列記します。直してほしい点は実のところ無数にありますが、今回は厳選して紹介します。ぜひ、多くの人たちに知っていただき、「そりゃ早く修正しなきゃね」という世論が盛り上がりますように願っています。順位を付けて記載していますがあくまで紹介する上での便宜上です。深い意味はまったくありませんが、運営支援としてなんとなくの感覚は反映しています。
(※基本的に運営支援ブログと社労士ブログでは、学童保育所について「放課後児童クラブ」(略して児童クラブ、クラブ)と記載しています。放課後児童クラブは、いわゆる学童保育所と、おおむね同じです。)
<すぐに変えてほしい第1位>
「補助金の負担の割合」を、国がもっと負担するように変えてほしい!
→放課後児童クラブを運営する(毎日、無事に開所ができる状態にあること)にはお金がかかります。そのお金は、補助金(国民が払う税金が由来)と、利用する保護者が支払う利用料(保育料など)の2つで成り立ちます。国は、児童クラブの運営経費については「保護者が全体の半分を負担してね。残る半分は、国と都道府県と市区町村が3分の1ずつね」となっています。これはあくまで国としての考え方を示したもので保護者が必ず運営経費の半分を負担してはいませんが、補助金の負担の割合は、国:都道府県:市区町村で3分の1ずつというのは、そうなっています。
(たとえば、1年間を3000万円で運営している児童クラブがあるとします。そのうち半分の1500万円は保護者さんが支払う料金でまかなってください、というのが国の考え方です。残る1500万円は、国と都道府県と市町村が3分の1ずつ、つまり500万円ずつ支払いましょう、というのが児童クラブの補助金の仕組みです。)
ここを変えてほしいというのが運営支援の希望第1位です。なぜかといえば、「市町村の多くがお金が無くて財政に苦しんでいるので、児童クラブの補助金の3分の1の負担でも後ろ向きになってしまう。それを防ぎたい」からです。
仮に、先の例で、国が3分の2を負担するとなれば1000万円で、残り500万円を都道府県と市区町村で負担するので250万円ずつとなります。こうなると、市区町村の負担は半減しますよね。運営支援は、もっと国が費用を負担して市町村の財政負担を軽減してほしいと訴えたいのです。
多くの市町村は財政事情が厳しいのです。その厳しい財政の中で、ごみ処理、道路などの公共インフラ、高齢者福祉などいろいろな事業があって、どうしても児童クラブは「まあ、こどもはなんとかなるでしょ」的な考えてその整備や投資の優先順位が高くならないんですね。子育て支援は大事だよといっても、小学校のDX化には熱心でも児童クラブを増やすことは優先順位が高くない。行政の、児童クラブに対する整備充実の重要性に関する理解を深めて行政における予算投下先の優先順位を高めることも大事ですが、先立つモノつまりお金を市町村が安心して使えるようになれば、児童クラブへの予算投下も拡大すると、運営支援は期待するのですね。
先の例では、1500万円を保護者が負担することになりますが、40世帯が利用しているクラブでは1か月あたり3万円以上の利用料となってしまいますから、それは保護者に負担を求めることはなかなかできません。現実に、児童クラブでは料金が高めのクラブでも月額2万円ぐらいです。では保護者の負担分で負担しきれない分はどうなるの? 2つしかありません。1つは「足りない分を市区町村がお金を出す。市区町村が一般の予算で児童クラブ運営分のお金を出す」。こうしてくれる自治体はありがたいのですが、「どれだけ補てんしてくれるかどうか」の問題があります。そしてもう1つは「足りない分はしょうがないので、足りない分はなかったものとして、あるだけのお金で運営してくれ」というものです。現実的にはこちらのほうが多いのではないでしょうか。
つまり、本来なら3000万円の予算で運営したいのに、保護者40世帯からは最大15000円しか徴収できません。すると年間で720万円になります。1500万円よりだいぶ少ないです。もう仕方がないので、補助金1500万円と、その720万円の合計の2220万円で児童クラブを1年間運営してね、ということになりがちなのです。
国が補助する割合を増やすと同時に、国が児童クラブの経費の半分を負担してほしいとしている保護者の負担の割合分もまた、減らすことが大事ですよ。国の負担分は、保護者の負担分を減らすことを想定して増やすことが大事なのです。実際には保護者の負担は全体の2分の1になっていないところがほとんどですが、この国の考え方があると、各地で「児童クラブの保育料を値上げします。というのは、国は半分を保護者が費用負担することを求めていまして」と利用料引き上げの理由としてよく使われるのです。わたくし萩原に言わせれば、「国がそういう考えだから」と国のせいにするのではなくて「実際に運営すると何万円足りないからその分、利用者にも負担してほしい」と正直に丁寧に説明するべきですよ。児童クラブは市町村事業なんですから市町村が責任を持って堂々と住民に説明しましょうよ。
ということで、補助金の負担の割合を、保護者負担が想定されている分も含めて見直すことで、児童クラブの整備が進まないとか、クラブが足りなくて待機児童が出てしまうとか、大規模状態でギュウギュウ詰めとか、職員の人数も増やせないとか、児童クラブをとても苦しめている多くの課題が解決に向かう道筋が付けられるのですね。
当面は保護者の負担を全体の10分の1、都道府県と市区町村も10分の1ずつとして、残る10分の7を国が負担することを目指したらどうでしょう。先の3000万円のクラブなら、保護者側の負担は300万円(40世帯なら月額6250円ですね)、都道府県と市区町村も300万円ずつ、2100万円を国が負担となります。その先さらに、市区町村の負担をさらに半分にして、市区町村が負担しなくなった分を国や都道府県が負担するように変えていけば、市区町村も安心して児童クラブへの予算を組むことができます。
こどもまんなか社会を目指すなら子育てを支える児童クラブの充実は必要です。だったら国は、お金を出しましょうよ。お金の負担の割合を変えるだけで、児童クラブの整備が一気に進む可能性はきっと高いと運営支援は考えていますよ。
<すぐに変えてほしい第2位>
「補助金の単価の額」を、引き上げてほしい!
→単純な希望です。児童クラブにはいろいろな種類の補助金が設定されています。その補助金は人件費の補助を主目的としています。いま、人を雇うには高い給料を用意しなければなかなか人が集まらないんですよ。とりわけ、きつい仕事であることが知られている児童クラブでは特に。人件費を増やすには、補助金の単価額が増えることが何より必要です。
たとえば2025年度、児童クラブで常勤職員2人を配置している場合は693万9000円です。以前よりだいぶ増えました。それでも急激な最低賃金の上昇や物価上昇にはとても追いつきません。常勤職員を2人雇うとそれで500万円は余裕でこえます。若手1人とベテラン1人の常勤なら350万円と500万円で850万円です。もう補助金が不足します。さらに児童クラブには5~10人ぐらいの非常勤職員が必要です。それで数百万円の予算が必要です。
ね、全然足りません。確かに児童クラブの補助金はこの十数年でぐんと増えました(それだけ以前は悲惨だったということ)が、今の世間の動きからすると足りないのです。最低でも2倍、安定した児童クラブ運営を実現するには、今の補助金単価の3倍にすることが必要です。そうすれば、児童クラブの事業の本旨をよく理解している優れた人材を多数確保することができ、児童クラブで児童を受け入れる時間を長くすることも、開所する日数を増やすこともできます。職員が多数確保されるので、クラブの長時間開所での職員への過重労働への負担も減りますよ。いいことづくめです。
児童クラブを安定させるには、1位と2位を同時に国が取り組めばきっと大丈夫でしょう。なお、「補助金を利益に変換する補助金ビジネスへの規制」も同時に必要ですからね。補助金が増えてもそれが、度を越して児童クラブ運営事業者の純利益になってしまったら税金の無駄遣いです。「事業を実施するに十分な人数の職員を、その職務に見合った正当な賃金を支払って、質の高い児童クラブ運営を実施してもなお生じた剰余金」については、どうぞ利益としてお納めください、とすればいいのです。それなら税金の不当な利用にはならないでしょう。
1位と2位だけでだいぶ長くなりました。
<すぐに変えてほしい第3位>
→放課後児童クラブを「児童福祉施設」に定義しなおすこと!
これは長期的な取り組みが必要でしょうが、のんきにしていてはなりません。先の1位、2位の改善にも大いに影響することです。いまの時代、多くの人たちに「放課後児童クラブは、家が留守の小学生を受け入れるために当然に自治体が設置する施設」と思われていますが、違います。児童クラブは、設置するもしないも、どのように運営するかも、すべて自治体(市区町村)の判断に任されています。設置してもしなくてもいい、任意の仕組みなのです。保育を必要とする住民がいる限り、設置しなければならない保育所と決定的に異なっているんですね。児童クラブは正式の事業名を「放課後児童健全育成事業」と呼びます。この放課後児童健全育成事業を行っている場所が放課後児童クラブです。それを学童保育所と呼んだり学童クラブや留守児童育成室と呼んだりしているんですね。
義務じゃないからこそ、いろいろなところで「緩く」なっているのが児童クラブなんです。補助金があまり高くないのも、その補助金を出す出さないも自治体が決められるというゆるさもまた、児童クラブが任意のシステムだからだと、わたくしは考えています。
ですので、児童福祉法を改正して、事業として定められている放課後児童健全育成事業を、児童福祉施設と定義しなおすことが何より大事です。これはもう、地方の議会でどんどんと意見書を決議して積み重ねて国会を動かすことで実現することを目指しましょう。小学1年生の半分が利用する社会インフラなんですから。しかも将来的には利用するこどもの割合はもっと増えるでしょう。それなのに、やるもやらないも任意のままの仕組みであることがやっぱりおかしいのですよ。メディアもぜひ児童クラブの改善のために児童福祉法改正についてキャンペーン記事を出していただきたいと期待します。
例によって長くなったので以下は項目だけ列記しておしまいにします。
<すぐに変えてほしい第4位> 放課後児童支援員の配置を義務化に戻すこと。(以前は義務だったんです!)
<すぐに変えてほしい第5位> 放課後児童支援員の資格体系の見直し。資格の専門性をもっと強化すること。国家資格の新設など。資格取得者への定期的な講習再受講など。
<すぐに変えてほしい第6位> 全事業者に「支援の単位」ごとの収支状況の公表を義務付け。これで補助金を利益に変えている事業者を浮き彫りにできます。
<すぐに変えてほしい第7位> 複数年度契約の場合の業務委託料や指定管理料の「物価等上昇分」のスライド制度の義務付け。
<すぐに変えてほしい第8位> 分かりにくい「処遇改善等事業」の補助金を廃止して運営費補助を単純に増額すること。「キャリアアップ処遇改善事業」は有資格者対象なので分かりやすいですが処遇改善等事業は分かりにくいうえ、結局、実施するかしないかは自治体任せ。確か3~4割程度の自治体しか利用していない補助金です。運営費という人件費への補助金がある制度にさらに人件費を補助する制度は止めて、運営費を増やせばいいじゃないですか。
<すぐに変えてほしい第9位> 小学校建物内へ児童クラブを設置する際は児童クラブが必要な状態なら優先して施設の場所を確保できるルールを国が決めることと、民間事業者の新規進出を支えるために施設の新規建設の費用の大半を補助する制度を作ること。
<すぐに変えてほしい第10位> 「こどもを預かる場所」という認識。この認識を捨てましょう。これは変えてほしいという第三者への要望より、児童クラブ側がまず率先して社会に呼びかけていくことが大事ではないでしょうか。確かにこどもの生命身体を受け入れる、つまり外形的には預かる行為をするのが児童クラブです。でも、児童クラブの本来の目的は「預かる」という形態の上に本当の目的があるわけですよ。健全育成だったり、あるいはスポーツや勉強などの支援だったり。放課後児童クラブとして事業を行い、その事業に見合う補助金を受けている事業に対しては「預かっている場所」という認識を捨てましょう。それは日常の1つ1つの言動から意識して行っていくことがあります。メディアの取り上げ方も重要です。もちろん、単に預かるだけの機能の施設だってこどもが過ごす選択肢としてあっても良いとわたくしは考えますよ。ただそれは児童クラブではない仕組みだということ。こどもが放課後や夏休みなどの休み中に過ごす場所は多彩であるべきですし、児童クラブに限られることでもないというのが運営支援のスタンスです。単に預かる場所だってあっていいとします。ただ児童クラブは「預かるだけの場所」ではないということを世間様に周知したい。だからこそ、カネも人材も必要なんですよ、ということです。最後はちょっと長くなりましたが、本当にね、これは伝えたいので、やっぱり長くなりました。
(お知らせ)
<社会保険労務士事務所を開設しました!>
2025年9月1日付で、わたくし萩原が社会保険労務士となり、同日に「あい和社会保険労務士事務所」を開業しました。放課後児童クラブ(学童保育所)を中心に中小企業の労務サポートを主に手掛けて参ります。なお、放課後児童クラブ(学童保育所)に関して、労働関係の法令や労務管理に関すること、事業に関わるリスクマネジメント、生産性向上に関すること、そしていわゆる日本版DBS制度に関しては、「あい和社会保険労務士事務所」を窓口にして相談や業務の依頼をお受けいたします。「あい和社会保険労務士事務所」HP(https://aiwagakudou.com/aiwa-sr-office/)内の「問い合わせフォーム」から、ご連絡のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
☆
「一般社団法人あい和学童クラブ運営法人」は、引き続き、放課後児童クラブ(学童保育所)の一般的なお困りごとや相談ごとを承ります。児童クラブの有識者として相談したいこと、話を聞いてほしいことがございましたら、「あい和学童クラブ運営法人」の問い合わせフォームからご連絡ください。子育て支援と児童クラブ・学童保育の運営者の方、そして行政の子育て支援と児童クラブ・学童保育担当者の方、議員の方々、ぜひとも子どもたちの安全と安心を守る場所づくりのために、一緒に考えていきましょう。セミナー、勉強会の講師にぜひお声がけください。個別の事業者運営の支援、フォローも可能です、ぜひご相談ください。
☆
(ここまで、このブログをお読みいただきありがとうございました。少しでも共感できる部分がありましたら、ツイッターで萩原和也のフォローをお願いします。フェイスブックのあい和学童クラブ運営法人のページのフォロワーになっていただけますと、この上ない幸いです。よろしくお願いいたします。ご意見ご感想も、お問合せフォームからお寄せください。出典が明記されていれば引用は自由になさってください。)