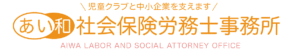放課後児童クラブ(学童保育所)の基礎知識シリーズ9は「就業規則」です。児童クラブでは必ず用意しましょう。
放課後児童クラブ(いわゆる学童保育所)運営者をサポートする「運営支援」を行っている「あい和学童クラブ運営法人」代表の萩原和也です。放課後児童クラブを舞台にした人間ドラマ小説「がくどう、 序」が、アマゾン (https://amzn.asia/d/3r2KIzc)で発売中です。ぜひ手に取ってみてください! 「ただ、こどもが好き」だからと児童クラブに就職した新人職員の苦闘と成長、保護者の子育ての現実を描く成長ストーリーです。お読みいただけたら、アマゾンの販売ページに星を付けていただけますでしょうか。そして感想をネットやSNSに投稿してください! 最終目標は映像化です。学童の世界をもっと世間に知らせたい、それだけが願いです。ぜひドラマ、映画、漫画にしてください!
放課後児童クラブの安定した事業運営に少しでもお役に立てれば、として掲載している基礎知識シリーズ。第9回目は、いわゆる日本版DBS制度への対応でも取り上げた「就業規則」です。就業規則はとてもややこしい決まりごとがありますが、とても重要な仕組みですから、運営する側も働く側も、就業規則をしっかり理解しておくことが大事ですよ。なお、あす10月14日の運営支援ブログは筆者所用のため休載となります。
(※基本的に運営支援ブログと社労士ブログでは、学童保育所について「放課後児童クラブ」(略して児童クラブ、クラブ)と記載しています。放課後児童クラブは、いわゆる学童保育所と、おおむね同じです。)
<就業規則とは>
(※この部分、10月10日に掲載した文章を再掲載しつつ、追加したり削ったりしています。)
就業規則について簡単に説明します。厚生労働省兵庫労働局のウェブサイトに分かりやすい説明がありましたので、一部引用します。(就業規則)
「職場において、使用者と労働者との間で、あらかじめ労働時間や賃金などの職場の労働条件や服務規律などをはっきりと決め、労働者に明確に周知しておくことが必要です。就業規則は、これらのことを文書にして具体的に定めたもののことです。」
「労働基準法では、パートタイマー等を含め常時10人以上の労働者を使用する事業場は、就業規則を作成し、その事業場を所轄する労働基準監督署長に届け出ることを義務付けています。なお、労働者10人未満の事業場でも、就業規則を作成整備することが望まれます。」
放課後児童クラブはとても小さい事業者も多いので、就業規則を作っていない事業者もあるでしょう。保護者会運営で働いている職員が最大でも5、6人という、1つの独立したクラブであるという場合です。とはいえ、上記の引用した説明からも、働き方のルールを定める就業規則は作成した方が良いです。また、保護者会運営の児童クラブで正規(常勤)職員が2人、週に1~5日、定期的に勤務シフトに入っている非常勤のパート、アルバイトが8人いるクラブでは「常時10人以上」になりますから、就業規則の作成が義務となります。また、常にシフトに入っている職員が8人で、夏休みだけ数人の学生アルバイトを雇っている場合は「常時10人以上」ではないので就業規則の作成義務はありません。
就業規則は「事業場」ごとに作るか、作らないかを考えます。児童クラブの場合、この「事業場」という捉え方が厄介だと運営支援は考えます。というのは、一般の企業で本社があって、別の市町村に支社があって工場があって、という場合、「本社」「支社」「工場」ごとに就業規則を作ることになるのです。働いている人たちの「かたまり、集団」が事業場という考え方になるからです。
ところが児童クラブの場合、1つ1つの児童クラブを「事業場」と捉える場合、常時10人以上の職員が働いている児童クラブはさほど多くはないでしょう。となると、就業規則は作成の義務がありません。一方で、複数の児童クラブを運営している法人や団体があって、給与の計算や経費の精算は運営本部や事務局で一括して行っている、あるいは職員配置シフトも運営本部や事務局で最終的に許可を得ているということになると(実際、そのような形態の児童クラブ事業者が多いでしょう)、1つ1つのクラブが「独立した事業場」とは言い難いでしょう。児童クラブの世界では複数の児童クラブを運営している法人や団体は、ほぼもれなく就業規則を作成しているようです。それはその方が便利だからですが、ということは1つ1つのクラブを独立した事業場とは考えず、法人や団体全体を1つの事業場として(無意識にしろ)考えている、ということになります。
これを運営支援がどうしてこだわっているかといえば、「事業場」単位で考えることが必要なことに、「衛生管理者」「産業医」「ストレスチェック」といった労働安全衛生法において求められることがあるからです。就業規則に関してはクラブ全体をまとめて、でも産業医やストレスチェックなどは「1つ1つのクラブごとに考えれば義務化となる50人に達しないから」というダブルスタンダードが横行しているのが児童クラブ業界であると運営支援には見受けられるからです。もっともストレスチェックはまもなくどの事業規模でも義務となりますが。
<児童クラブは多彩な働き方が必要。だからこそ就業規則が必要>
児童クラブは他の業界と異なり、働き方が多種多様です。例えばスーパーマーケットであれば開店時刻や閉店時刻は基本的に1年を通して同じですね。多少、年末年始に違いがあるかもしれませんが。
児童クラブは、小学校の授業がある期間と、長期休業期間中では、職員の勤務する時間帯が大幅に異なります。また、小学校の授業ある期間であっても、こどもが登所する前の時間帯、例えば午前中に研修や会議が設定されることも通常にあります。そのような時間は勤務なのかどうかもまた明確にされておかねばなりません。トラブルのもとになりますからね。
他の業界と働き方がかなり異質な児童クラブでは、職員の働き方を丁寧に示す就業規則が必要です。授業がある日は午後1時から午後7時まで、長期休業期間中は午前8時から午後7時までが勤務時間ですよ、という決まりを設けることが必要です。それが就業規則です。まして、長期休業期間中は労働時間を延ばすという変形労働時間制度を設ける場合は就業規則がなければそもそも設定できません。
<就業規則は、それなりに「強い」>
「働く(労働)」ことに関してはいろいろな決まりがありますね。労働基準法という法律のことは内容までは知らなくても名前は聞いたことがある人が多いでしょう。それら、いろいろな決まりには、その強さが決められています。強い順に書いていくと、こうなります。
法令(労働基準法など)>労働協約(使用者側と労働組合が結ぶ契約、約束ごと)>就業規則>労働契約(雇う側と、働く人それぞれの個別の契約)
これを簡単に言うと、「就業規則に書かれていないことは法令の決まりに従う」ことですし、「法令に書かれていない内容の手厚い福利厚生を職員対象に実施したくても就業規則に書かれていないことはできない」ことにもなります。例えば、児童クラブで流行しやすいインフルエンザに職員がかかって職員が仕事を休むにあたって、3日間は特別に有給の休暇を与えようと児童クラブ事業者が決めても、法令にはそのような決まりはないので、就業規則に規定がなければ実施できません。
また、就業規則の方が労働契約より「強い」ということは、例えば先のインフルエンザの3日間有給休暇を例にすると次のようになります。就業規則に「すべての職員を対象とする」と書いてあれば、個々の労働契約において「インフルエンザの3日間有給休暇は与えない」という契約で雇われた職員がいたとしても、就業規則の方が強い効果があるので、労働契約に「インフルエンザ3日間有給休暇なし」とあってもその権利は行使できる、ということです。
労働契約に書かれていない、あるいは労働契約の内容が就業規則で定められた内容に達しない場合は、就業規則に書かれている部分が労働契約の中身となるのです。これを「最低基準効」と呼んでいます。就業規則に試用期間1か月とあるのに、ある人だけ試用期間6か月となっている労働契約を結んだとしても、就業規則の内容が有効となるのです。1か月より6か月の場合が不利ですからね。仮に、特定の経歴の人だけ6か月の試用期間としたいのなら就業規則にて定める必要がある、ということです。(それも不合理な理由ではもちろん認められません。いくら児童クラブで女性の働き手が欲しいからといって男性の応募を減らす目的で、就業規則で試用期間を女性は1か月だけれど男性は6か月、という内容にしても、それは差別的ですので認められません)
法令は、細かいところまでなかなか書いていないので、いろいろな出来事に対応するためには就業規則をなるべくきめ細かく書いておくことが必要です。その典型的な例が、職員を処分するときに必要な懲戒に関する決まりです。
児童クラブはその事業の特質から、他の問題行為よりも、こどもに対しての不適切な行為については厳しい対応、処分を課す事業者が多いようです。例えば、クラブのこどもに不適切な行為をしたらいきなり減給や自宅待機処分、場合によっては諭旨解雇をする一方で、他のトラブル(職務専念違反や暴力行為など)には始末書、厳重注意処分とするような場合です。こどもへの不適切な行為についてのみ処分を重くしていると全体的にバランスを欠くように見えますが、こどもの人権を守る場所であるということからあえてそのような処分にしたいと思っても、そういう趣旨を説明した就業規則類がなければ、実施できません。
就業規則はそれなりに強いルールです。ですから、きめ細やかな事業運営をするには必要不可欠です。
<就業規則は、単に働き方を定める決まりではない>
就業規則は職員の働き方を決めておく大事なルールです。児童クラブの事業者は保護者会や運営委員会など任意団体であっても、1クラブ1法人の小さな事業者であっても、ぜひとも就業規則は作っておきましょう。就業規則がないクラブで、仮に仕事に関してトラブルや問題があったら、それは労働基準法などの法律に従って解決、対応することになります。それは案外と事業者にも働く側にも不利な影響を及ぼすことがあります。
しかし、実は単に働き方を決めておくことだけが就業規則の役割ではありません。2つのもっと大事な役割があります。
1つは「雇う側(使用者側)の勝手な経営、運営を防ぐためです。就業規則は次の紹介にあるように、作るのは使用者側ですが、その作成には働く側の意見を聴取して作るようになっています。(働く側の同意や許可までは求められていませんが)。ですので、「まっとうな」就業規則であれば働いている側の意見も程度の差はあれ反映されていると考えられます。特に児童クラブは、「人」で成り立っている業態ですから、働いている人の意見や考え方がしっかり反映された就業規則であることが望ましい。使用者側の一方的な要求だけが反映されている就業規則では困るのです。
もう1つは「就業規則は会社、法人、団体の目指す方向性を現している」ということです。つまり「会社、事業者の性格を示している」といえるでしょうか。
児童クラブの事業者の就業規則であれば、「どのような事業者であることを目指しているか」「児童クラブの業界において、どのような事業者であることを示したいか」、その方向性をビシッと定めて事業者全体を導いていくのが、児童クラブにおける就業規則の役割です。こども、そして子育て中の保護者を支える社会インフラである児童クラブであるからこそ、働きながら子育てをしている職員のワークライフバランスを大事にした働き方を保障する就業規則である、ということを打ち出すことができます。
ですから就業規則は、使用者側が作成するものであっても、しっかりと働く側の意見を聞いて作成するべきです。とりわけ児童クラブの事業者は、児童クラブの職員(クラブの現場も、運営本部の事務職員も)の代表者から意見を聞いたり交わしたりしつつ、就業規則の案を作成していくことが大切でしょう。なお、状に10人に満たない職員しか働いていない小さな事業者では就業規則の作成は任意ですから働く側の意見を聴取することも義務にはなりません。しかしそういう場合でもクラブで働く職員の意見を聴きながら就業規則の作成に取り掛かるほうがよいでしょう。
<作り方、変更の仕方>
就業規則に関してはネット検索すれば厚生労働省の「モデル就業規則」をはじめとして、すでに出来上がった「ひな形」も多数入手できます。それらを利用するのももちろん良いのですが、就業規則というものは「その事業者、その会社にとって、目指すべき職員労働者の働き方」を決めるものですから、どの事業者も必ずや持っているであろう、それぞれの目指すべき雇用労働条件、雇用労働環境を反映させた「オリジナルの就業規則」を用意することがベストです。それには社労士や弁護士の専門家に依頼することが(お金はかかりますが)確実です。
そして就業規則は、すぐに作れたり変更できたりするものではありません。いろいろな段階を経なければできません。どのような流れで作成(または変更)となるか紹介します。就業規則には、事業者の目指す理想の働き方が盛り込まれます。つまり事業者の性格、カラーをしっかりと把握することがスタートです。休日数が多い事業者なのか、メリハリの利いた労働時間を特徴とするのか、ワークライフバランス重視で給料はそこそこだけれど休日休憩休暇が充実しているのか、経営側は、どのような事業者像であるかを把握することが重要です。
「これから作成する(又は変更する)就業規則で、使用者側はどのような事業者になることを目指すのかをイメージする。また、働く側はどのような働き方となり、事業者にどのような状況をもたらすことになり、事業者が目指す目的が確実に実現できるかどうかも、経営側がしっかり確認する。」
↓
「事業者側が就業規則の作成(または具体的な変更、改正)作業に取り掛かる。」
↓
「雇っているすべての職員、労働者の過半数の信任を受けた代表者を決める。また、すべての職員を対象に、就業規則の作成・変更について説明会をし、理解を得ることに努める。過半数の職員、労働者が加入している労働組合があればその労働組合の理解を得ることに努める。」
(労働者数が常時10人に達しない事業者もなるべく働く側の意見を求めましょう。)
↓
「事業者が理事会などで就業規則を決定する。」
(※就業規則の作成や変更に関して、職員側の同意や許可は絶対に必要ではありません。事業者側の案に職員側が賛成しなくても作成・変更は可能です。ですが、児童クラブは事業者側と職員側(労働者側)の「距離感」が近いですし、何より、職員が安心して日々の業務に取り組めるためのルールですから、できる限り、働いている職員の理解、合意を得る努力をしましょう。)
↓
「就業規則(変更)届を作成する」(社労士に任せるのが安心です。社労士なら条件が整えば電子申請もできます。)
↓
「就業規則(変更)届と、作成・変更した就業規則と、職員の意見書を、管轄の労働基準監督署に届け出ます。正副つまり2部作成します。この意見書とは、職員の過半数代表者か、過半数の職員が加入する労働組合の代表者の意見を聴取した内容の書面です。」(なお、意見書の内容が「変更内容に同意できない」という結論であっても、届出は受理されます。)
↓
「事業者は、作成・変更となった就業規則について、その内容を公開し、すべての職員にしっかり説明する。いつでもその就業規則を職員が見られるようにしておく。」(これを「周知」といいます。就業規則を作ったり変更したりしても、この周知が不完全ですと、就業規則の効力は否定されることが裁判所によって示されていますから、とても大事なプロセスです。本日のブログ最後にも記します。)
以上のことから、就業規則の作成・変更はとても多くの順序を踏まえて行われる作業です。時間がかかるのです。児童クラブの場合、職員への内容の説明周知をしようにも、職員が大勢集まれる機会はなかなか持てません。就業規則(変更)案の作成にしても、例えば保護者(OBも含む)が集まって運営方針を決めている保護者運営系の児童クラブであれば、それが法人化されている事業者であっても、役員が集まれる機会が月1回、それも夜の数時間の会議時間しか取れないとなれば、協議検討だけでも数か月は必要です。
<必ず盛り込まねばならないことがあります>
就業規則には、必ず盛り込まねばならない「絶対的必要記載事項」と、必要に応じて盛り込む「相対的必要記載事項」があります。絶対的必要記載事項が欠けている就業規則は作成義務違反となりますが、就業規則に盛り込まれている内容については効果があります。
絶対的必要記載事項は「始業・終業時刻」「休憩時間、休日、休暇」「賃金の決定・計算・支払い方法」「賃金の締め切り・支払い時期」「昇給」「退職(解雇事由を含む)に関する事項」があります。
相対的必要記載事項は、ある制度を事業者が実施する場合には就業規則に盛り込むことが必要なもので、主なものに「退職手当」「臨時の賃金」「表彰・制裁」があります。
これらのチェックは、専門に学んだ人ではないとなかなか難しいものです。就業規則の作成は社会保険労務士や弁護士に依頼することが確実でしょう。依頼された側は、単に規則をポンポンと作ることはしません。その事業者がどのような働き方を職員にしてほしいのか、将来的にどのような事業者を目指すのか、社会からどう評価される事業者になりたいのかを、じっくりと話を聞いたうえで就業規則を作っていきます。専門家に頼んだからといって数日や1週間で完成するものではありません。その点、誤解が多いようですが、専門家ほど慎重に丁寧に就業規則を作成することを心がけます。だからこそ、就業規則の作成に係る費用はそれほど安くはないのですね。
<賃金や懲戒もハラスメント対策も就業規則>
就業規則で誤解されやすいのは、「就業規則」ではない名称の決まりも「就業規則の一部」であるということです。例えば、職員の給与や賃金について、別途「給与規程」という名称の決まりを作成している児童クラブ事業者は珍しくありません。その給与規程も就業規則です。ハラスメントの対策は最も大切とされる決まりですが、それもまた就業規則を構成します。
よく就業規則の中に「~については別途定める」「~については賃金規程において定める」という文言を載せて、当該就業規則には細かい決まりを載せていない場合があります。この場合、別途定めるとされている決まりもまた就業規則となります。つまり、就業規則本体と一緒に労働基準監督署に提出することが必要です。まして、別途定めるとあってもその定めが存在しない、ということは実はままありがちです。注意したいですね。
賃金の決まりや表彰、懲戒について定める決まりはとても重要です。特に懲戒については、きめ細かい決まりがないと職員を対象にした処分はできません。「こどもに対して問題ある行動をした者は解雇する」という程度の決まりではダメです。具体的に、何をどうしたら解雇する、減給する、ということがなければ、その決まりは通用しません。通用しているように思えるのは、そのような「雑な」ルールで決められたことでも(内心では不満ながらも)従っている職員ばかりだからです。仮に「あまりにも処分が重すぎる」として裁判を起こしたら、雑なルールで処分を決めた側は、まず負けます。逆に、きめ細かく書かれたルールに従って解雇された、減給処分になったという場合はなかなかひっくり返しようがありません。もっとも、その決まりそのものが不合理である場合はダメですよ。
このあたりこそ、社労士や弁護士と相談しながら就業規則、とりわけ懲戒に関する規定を作ることが大切です。
<周知こそ大切だと周知したい>
就業規則はその職場における「守らねばならないルール」です。一般的に法令というのものは「知らない」からといって通用しない、ということはありません。人を故意に殺害した人が「殺人罪なんて知らない」と主張しても通用しないのは当然でしょう。
しかし就業規則は違うのです。その事業場において働く人たちが「知らない」就業規則は、その効果が否定されるのです。これは最高裁判所が判決で明確に認めています。前にも触れた「周知」がなされていない就業規則はその効果が認められないのです。せっかく、丁寧なプロセスを経て就業規則を作ったり変えたりしても、働いている職員が就業規則の内容を知る機会を確保されていなければ、通用しないんですね。
ただし、これは個々の職員が「知らなかったこと」で判断されるのではありません。誰しもが知る機会があって容易にその内容を理解できるような状態であるならば「周知した」となります。例えば児童クラブ事業者が職員を対象に数時間もの時間をかけた就業規則の説明会を開いて、かつ、就業規則の全文を職場で容易に確認できるようにしていたとき、職員が自分の意志で就業規則を知ろうとしなかったとか、説明会に参加したけれど頭の中では別のことを考えてさっぱり話を聞いていなかったということで就業規則を知ることがなかったとしても、それは「周知したこと」に入ります。
特に「不利益な変更」のときは注意してください。就業規則の変更によって働く側にとって不利益なことがもたらされることがあります。そのようなことが一方的になされることは許されませんが、合理的な理由があっての不利益な変更でああれば、個々の労働者、職員もその変更に従うことになります。非常に重要な考え方ですが、この不利益な変更の場合には「周知」が絶対に欠かせないからです。そして不利益に変更する際の合理性と周知は事業者側に立証の責任があるのです。(労働契約法第9条と第10条)
児童クラブの事業者は、これから日本版DBS制度への対応として就業規則を変更したり、あるいは新たに作成することが多いでしょう。その際は、ただ単に変えた、作っただけではなくて、しっかりと職員がその内容を知ることができるようにしてください。この制度は場合によって、それまでしっかりと真面目に働いていた人を急に激変の状況に置くことになるかもしれない厳しい制度です。つまり働く側にとって予想以上の不利益を及ぼす可能性があります。ですから、日本版DBS制度への対応を盛り込んだ就業規則類を作った、あるいは対応して変更したという事業者は、この「周知」を丁寧にしていただきたいと運営支援は望みます。専門家に説明や周知の方法の策定を任せることも良いでしょう。ぜひ検討してくださいね。
(お知らせ)
<社会保険労務士事務所を開設しました!>
2025年9月1日付で、わたくし萩原が社会保険労務士となり、同日に「あい和社会保険労務士事務所」を開業しました。放課後児童クラブ(学童保育所)を中心に中小企業の労務サポートを主に手掛けて参ります。なお、放課後児童クラブ(学童保育所)に関して、労働関係の法令や労務管理に関すること、事業に関わるリスクマネジメント、生産性向上に関すること、そしていわゆる日本版DBS制度に関しては、「あい和社会保険労務士事務所」を窓口にして相談や業務の依頼をお受けいたします。「あい和社会保険労務士事務所」HP(https://aiwagakudou.com/aiwa-sr-office/)内の「問い合わせフォーム」から、ご連絡のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
☆
「一般社団法人あい和学童クラブ運営法人」は、引き続き、放課後児童クラブ(学童保育所)の一般的なお困りごとや相談ごとを承ります。児童クラブの有識者として相談したいこと、話を聞いてほしいことがございましたら、「あい和学童クラブ運営法人」の問い合わせフォームからご連絡ください。子育て支援と児童クラブ・学童保育の運営者の方、そして行政の子育て支援と児童クラブ・学童保育担当者の方、議員の方々、ぜひとも子どもたちの安全と安心を守る場所づくりのために、一緒に考えていきましょう。セミナー、勉強会の講師にぜひお声がけください。個別の事業者運営の支援、フォローも可能です、ぜひご相談ください。
☆
(ここまで、このブログをお読みいただきありがとうございました。少しでも共感できる部分がありましたら、ツイッターで萩原和也のフォローをお願いします。フェイスブックのあい和学童クラブ運営法人のページのフォロワーになっていただけますと、この上ない幸いです。よろしくお願いいたします。ご意見ご感想も、お問合せフォームからお寄せください。出典が明記されていれば引用は自由になさってください。)