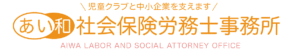3分30秒で読めます! 運営支援ブログ&社労士ブログの短縮版(2025年9月7日~9月13日)
「一般社団法人あい和学童クラブ運営法人」と「あい和社会保険労務士事務所」では、それぞれ「運営支援ブログ」と「社労士ブログ」で、放課後児童クラブ(いわゆる学童保育所)全般に関して提言や意見を行っています。2025年9月7日から9月13日までに掲載した両ブログ(運営支援ブログ、社労士ブログ)の内容をご紹介します。興味がそそられるテーマがございましたら、ぜひその日のブログをご高覧ください。
※放課後児童クラブを舞台にした、人間ドラマであり成長ストーリーの小説「がくどう、 序」が、アマゾンで発売中です。ぜひ手に取ってみてください! (https://amzn.asia/d/3r2KIzc)
※基本的に運営支援ブログと社労士ブログでは、学童保育所について「放課後児童クラブ」(略して児童クラブ、クラブ)と記載しています。放課後児童クラブはおおむね学童保育所(放課後児童健全育成事業を行っている施設に限る)と同じです。
・放課後児童クラブの基礎知識シリーズの7回目「労災(ろうさい)」です。シリーズ6回目(2025年7月26日掲載)で「けが」を取り上げ、労災についても説明していますが、掲載後も児童クラブ関係者から労災について何度か問い合わせを受けた経験から「働いている多くの人は労災がどういうことなのか理解している人は少ない。労災という単語は知っていても、それがどういうことなのか、何をしたらいいのか、実は知らない人が案外と多いのだ」ということを痛感しました。「人生で初めてアルバイトをしています。児童クラブでバイトを始めました」という高校生でも「読んでいただければ」分かるように説明していきます。(9月8日掲載・運営支援ブログ)
・放課後児童クラブでは、それなりに行われている「意向調査」。来年度も勤務を続けますか、それとも年度末で退職しますか? を調べる調査です。この意向調査そのものは、良いともダメとも言えません。必要な事業者なら実施すればいいことです。意向調査が例えば秋口、9月や10月に行われると早すぎる弊害がありそうです。「もう辞めるんだ」と職員自身に覚悟させること。「辞めようかな、どうしようかな」と悩んでいる職員はその悩みを長いこと抱えていることがあります。一度、「来期は継続しません」と回答すると、踏ん切りがつくことになるでしょう。そのまま年度末までしっかりと業務に向き合ってくれれば別にまったく問題はないのですが、その踏ん切りがさらに「こんな会社、早く辞めたい」という意識を加速させてしまうと、年度末を待たずに年末や賞与を得てから退職、という行動を招きかねないという「不安」を運営側にもたせる可能性は、あります。もちろん、いつ辞めたっていいんですよ。退職、転職、それは働く人が自由に決めることですから。(9月9日掲載・運営支援ブログ)
・来年度(2026年、令和8年)の児童クラブ入所手続きの案内をしている自治体が増えてきました。児童クラブの入所手続きを忘れてしまった、入所手続きの必要性を知らなかった、そのために児童クラブに4月から入れなかったという悲劇をゼロにしたいのです。なお、10月にもなるとほとんどの自治体で新規入所の案内をしますから、来年4月にこどもが小学1年生になる子育て世帯は、とにかく、児童クラブの新規入所情報を必ずチェックしましょう。自治体や児童クラブ事業者は「普通の保護者なら自分で情報をキャッチする」と思わないで。「普通」は、誰にでも当たり前のことではないのです。(9月10日掲載・運営支援ブログ)
・2025年10月1日から、育児・介護休業法の改正に伴って子育て支援に関するいくつかの対応を事業者が実施することが義務となります。児童クラブの事業者も、職員を雇って働いてもらっている限り守らねばなりません。その1つに、「3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関して」児童クラブの事業者の義務となるのが「育児期の柔軟な働き方を実現するための措置」の実施です。具体的には、次に紹介する5つの「選択して講ずべき措置」のうち2つ以上を、3歳から小学校に入るまでのこどもを育てている児童クラブ職員が選択できるようにしておくことが、義務となります。
1 始業時刻等の変更
2 テレワーク等(10日以上/月)
3 保育施設の設置運営等
4 就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇 (養育両立支援休暇)の付与(10日以上/年)
5 短時間勤務制度
(9月11日掲載・社労士ブログ)
・2025年10月1日から、育児・介護休業法の改正に伴って介護に関するいくつかの対応を事業者が実施することが義務となります。介護離職を防止するために導入された施策と、育児に関しても2025年4月から施行されている施策を紹介します。その中には、「子の看護休暇」の制度が2025年4月1日から「子の看護等休暇」と「等」の文字が追加されて変更されたことがあります。休暇を取得できる事由に「感染症に伴う学級閉鎖等」が加わったこと、「入園(入学)式、卒園式」が追加されたからです。学級閉鎖については自分のこどもが感染していなくても、つまり健康でいても学級閉鎖で自宅待機しなければならない状態でも認められます。ちょっと残念なのは入園入学式や卒園式です。そのときに使えるのはいいんですが、「式典」に限られます。(9月12日掲載・社労士ブログ)
・児童クラブの事業者は「カスタマーハラスメント対策」が義務となります。具体的には、カスハラ対応に関するルールを作ったりマニュアルを作ったりして、事業者としてどのように対応するか等を決める必要があります。これは「労働施策総合推進法」と呼ばれる法律が2025年6月に改正されて義務付けられたからです。2026年12月までの間にこの法律の内容が実施されることになりました。児童クラブのカスハラ問題の考察も紹介しています。(9月13日掲載・社労士ブログ)
〇2024年3月19日から始めた全国放課後児童クラブデータベースですが、最後となる埼玉県蕨市まで到達し、1巡目が終了しました。2025年9月から2巡目に突入しています。2巡目の確認事項は特設ページで順次、掲載していきます。また、2巡目の調査で新たに確認したデータは、1巡目の投稿記事に反映させていきます。
(お知らせ)
〇弊会は、次の点を大事に日々の活動に取り組んでいます。
(1)放課後児童クラブで働く職員、従事者の雇用労働条件の改善。「学童で働いた、安心して家庭をもうけて子どもも育てられる」を実現することです。
(2)子どもが児童クラブでその最善の利益を保障されて過ごすこと。そのためにこそ、質の高い人材が児童クラブで働くことが必要で、それには雇用労働条件が改善されることが不可欠です。
(3)保護者が安心して子育てと仕事や介護、育児、看護などができるために便利な放課後児童クラブを増やすこと。保護者が時々、リラックスして休息するために子どもを児童クラブに行かせてもいいのです。保護者の健康で安定した生活を支える児童クラブが増えてほしいと願います。
(4)地域社会の発展に尽くす放課後児童クラブを実現すること。市区町村にとって、人口の安定や地域社会の維持のために必要な子育て支援。その中核的な存在として児童クラブを活用することを提言しています。
(5)豊かな社会、国力の安定のために必要な児童クラブが増えることを目指します。人々が安心して過ごせる社会インフラとしての放課後児童クラブが充実すれば、社会が安定します。経済や文化的な活動も安心して子育て世帯が取り組めます。それは社会の安定となり、ひいては国家の安定、国力の増進にもつながるでしょう。
放課後児童クラブ(学童保育所)の運営支援は、こどもまんなか社会に欠かせない、あらゆる児童クラブを応援しています。
☆
運営支援からの書籍第2弾として、放課後児童クラブを舞台にした小説「がくどう、序」を発売しました。埼玉県内の、とある町の学童保育所に就職した新人支援員が次々に出会う出来事、難問と、児童クラブに関わる人たちの人間模様を、なかなか世間に知られていない放課後児童クラブの運営の実態や制度を背景に描く小説です。新人職員の成長ストーリーであり、人間ドラマであり、児童クラブの制度の問題点を訴える社会性も備えた、ボリュームたっぷりの小説です。もちろんフィクションですが、リアリティを越えたフィクションと、自信を持って送り出す作品です。残念ながら、子どもたちの生き生きと遊ぶ姿や様子を丹念に描いたハートフルな作品ではありません。大人も放課後児童クラブで育っていくことをテーマにしていて、さらに児童クラブの運営の実態を描くテーマでの小説です。児童クラブの運営に密接にかかわった筆者だからこそ描ける「学童小説」です。ドラマや映画、漫画の原作にも十分たえられる素材だと確信しています。
☆
「あい和学童クラブ運営法人」は、学童保育の事業運営をサポートします。リスクマネジメント、クライシスコントロールの重要性をお伝え出来ます。子育て支援と学童保育の運営者の方、そして行政の子育て支援と学童保育担当者の方、議員の方々、ぜひとも子どもたちの安全と安心を守る場所づくりのために、一緒に考えていきましょう。セミナー、勉強会の講師にぜひお声がけください。個別の事業者運営の支援、フォローも可能です、ぜひご相談ください。
☆
「あい和社会保険労務士事務所」は、放課後児童クラブ事業者様の経営の改善、事業運営の効率化、また児童クラブで働く人たちや運営に関わる保護者(会)の雇用労働条件や運営ノウハウのより良い改善のために、専門的な見地で助言、アドバイスを行います。また、中小企業様の労務関係の改善にご尽力いたします。児童クラブの方、埼玉県内の中小企業の方はぜひとも顧問契約をご検討ください。
☆
(ここまで、よくぞこの大変長いブログをお読みいただき誠にありがとうございました。少しでも共感できる部分がありましたら、ツイッターで萩原和也のフォローをお願いします。フェイスブックのあい和学童クラブ運営法人のページのフォロワーになっていただけますと、この上ない幸いです。よろしくお願いいたします。ご意見ご感想も、お問合せフォームからお寄せください。出典が明記されていれば引用は自由になさってください。)