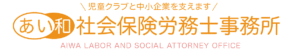放課後児童クラブ(学童保育所)を利用する人、職員へのヒント。「児童クラブのトリセツ」シリーズ18は「ちょっとした気配り」。円滑な関係性を目指しましょう。
放課後児童クラブ(いわゆる学童保育所)運営者と働く職員をサポートする「あい和学童クラブ運営法人」代表の萩原和也です。放課後児童クラブを舞台にした人間ドラマ小説「がくどう、 序」が、アマゾン (https://amzn.asia/d/3r2KIzc)で発売中です。ぜひ手に取ってみてください! 「ただ、こどもが好き」だからと児童クラブに就職した新人職員の苦闘と成長、保護者の子育ての現実を描く成長ストーリーです。お読みいただけたら、アマゾンの販売ページに星を付けていただけますでしょうか。そして感想をネットやSNSに投稿してください! 最終目標は映像化です。学童の世界をもっと世間に知らせたい、それだけが願いです。ぜひドラマ、映画、漫画にしてください!
放課後児童クラブ、学童保育所で働く人、運営する人、そして利用する保護者さん、それぞれにそれぞれの立場や事情があるのは当然ですし、求める要求も違って当然。ですから意見がすれ違ったり対立したりすることもこれまた当然。人が、人と向き合って過ごす場所であり環境ですからささいなことで人間関係にささくれができるのもありがち。そんなややこしい人間関係の場、濃密なコミュニケーションが求められる場所が、児童クラブです。それでも、基本的には人が人を思いやる、とても温かな場所であるのが児童クラブですから、その温かさを保つために必要な「ちょっとした気配り」を、それぞれの立場で意識して実行していけば、もっともっとあったかい場所になりますよ!
(※基本的に運営支援ブログと社労士ブログでは、学童保育所について「放課後児童クラブ」(略して児童クラブ、クラブ)と記載しています。放課後児童クラブは、いわゆる学童保育所と、おおむね同じです。)
<その76:児童クラブ職員側から保護者へは「普段からこまめな声掛け」をしよう>
児童クラブを利用している保護者から運営の立場にいる者が時々、言われることに「普段は何も伝えてこないのに、何か問題やトラブルがあったときだけ、ことさらに伝えてくる。以前から気にしていたということも言われる。だったら以前から話をしてくれたらよかったのに」という困りごとがあります。こどもを迎えに行ったときには挨拶程度だけ、何かあったときは深刻な顔の職員からあれもこれも言われてしまうことが、「話をされるのは当たり前で仕方のないことだけれど、何か釈然としない」という気分を抱きがち、なのですね、保護者としては。
ですから、児童クラブの職員は、普段からこまめに、どんな小さなことでも伝えることを心がけましょう。つまり「コミュニケーションを取っておこう、維持しておこう、できれば徐々にコミュニケーションを深めていこう」という心がけが必要だ、ということです。いまは連絡アプリでメッセージを個別に送れる時代ですが、それも活用しつつ、迎えに来た保護者と顔を合わすことができたどの職員も、一言二言、声をかけましょう。「いつも声掛けしているけれど、ろくに顔を合わせようともせずに、話を聞いているのかいないのか分からないで、すぐにこどもを連れて帰っちゃう親ばかりなんですけど!」という現場の怒りの声があるのも分かりますが、大事なことは「職員であるあなたが、声をかけること。関係を築こうという姿勢を見せること」です。それが実を結ばない相手だって、そりゃいますよ。人間なんて十人十色なんですから。でも、それでも声をかけ続けましょう。だって、児童クラブは、人と人が交わっていく場所なんですからね。
<その77:児童クラブ職員側から保護者へは「こどもが、どんな小さなことでも進歩、前に進んだことがあれば、褒めて伝える」こと。>
これもまた、保護者から言われたことがある児童クラブ側の人がいるでしょう。「問題やトラブルを起こしたことで、あれこれ指摘されるのは仕方がないと分かっている。でも、そんなときしか話しかけてこないんですよ、クラブの先生は!」
児童クラブは、こどもが育つ場所です。遊びによって他者との関わり方や自主性など、集団での生活行動によって規律や作法などを会得していきます。失敗だって当然あります。児童クラブの職員は、えてして、とても忙しい(それはこどもの育ちぶりや行動をしっかり把握するのにはとても職員数が足りない、つまり1人の職員であれもこれもやらねばならないので、とても1人1人のこどものことを把握できない、向き合えないという、つらい現実)ので、特に何もなかったと感じた日や、「年齢相応に、そういうことはできるよね」と自分なりに「それは通常のこと」と判断したことについては、わざわざ保護者に伝えない(というか、伝えようとしてもやむなく他の仕事が優先されてしまう)ままで、「これは説明しておかないと大変だ」というトラブルがあったときにだけ、迎えに来た保護者に「ちょっとお話があるんですが」と呼び止めることに、なりがちです。わたくし萩原もそういう現実は承知しております。
おりますが、でもあえて現場の職員のみなさんにお願いしたい。「当たり前にできたことでも、その子が、なかなかできなかったことだったり、初めてのことを成し遂げたなら、必ず保護者に、その子の成長を喜びを交えて伝えてあげてください。もっと言えば、ごく普通に何もなく平穏に過ごせたそのことすらもプラス評価を交えて伝えてあげてください」と。
たった十数秒でいいんです。できたら30秒ぐらいで。もっとできたら1分ぐらいで。「こんなことができたんですよ、すごいですね」とか「頼りになる場面があったんですよ。おうちでもそうなんですか? いやぁさすがですねお母さん!」とか、とにかく、こどもにももちろんですが、保護者も、できるだけ褒めてあげてください。日々のワークライフバランスに苦慮している保護者さんを褒めてねぎらってあげてください。
<その78:トラブルや困ったことこそ、「事実」を「すぐに」そして「丁寧に」>
誰しもやりたくはない「困ったことの報告」「トラブルの連絡」。拙著「がくどう、 序」にも、こどもに大けがをさせた職員の苦悩と、当然に不備を指摘する保護者の様子を描いていますので、ご覧ください。1年間、どんなに小さなトラブルでも何1つ起きない児童クラブなんて、まずありえません。あるとしたらその児童クラブはこどもたちに何もさせていない監獄のような児童クラブか、ウルトラ奇跡の児童クラブです。ウルトラ奇跡の児童クラブさんはぜひ、どうやってこどもたちと関わり合い、職員同士で育成支援の相互理解をしているかご教授ください!
さて、トラブルや困ったこと、とりわけ「加害者側のポジションに立ったこども」の保護者には、当然ながら、再発防止の相談も含めていろいろと相談しなければなりません。トラブルはどんな小さなことでも伝えねばなりませんよ。
鉄則は「事実」を「すぐに」、「丁寧に」伝える、この3点です。
事実というのは、その時点において「まず間違いがなかろう」という事柄です。調べている最中のことは事実ではないので、「いままだはっきりしていないのですが」と注釈を付けねばなりませんし、「それは急いで聞き取り調査などを行って、事実が確認でき次第、直ちに報告します」というように伝えることが肝心です。事実が事実となっていない段階で事実として伝えてしまうと、のちほど「実は本当はこういうことでした」と事実を修正する段階において「あなたたち、しっかり調べてくれていなかったんですか!」と保護者の不信感をただ増大させるだけになります。事実でないこと、分からないことは遠慮なく分からないと伝えながら、「いま、把握していること」「いま、取り組んでいること」を伝えましょう。
すぐに、というのは分かりやすいですね。「きょう起きたトラブルは、今日中に解決する」が児童クラブの掟です。そうしないと、事実にたどりつくことが難しくなり、当事者たちの感情は複雑にいがみあって拡大し、収拾がつかなくなります。解決できなくても解決の糸口をはっきりとつかむまで事態収拾に取り組むことは当然です。そもそも、児童クラブで起きた小さなトラブルを職員から知らされないで、こどもから聞かされる保護者は大勢いるでしょう。わたくしだって経験があるほどです。仕方ないのですが、こどもの口から語られることは「事実」とは離れた内容のこともごく普通です。本当のことを言ったら親に叱られるから、ちょっと曲げて話すとか盛って話すとか、ありますよ。事実とは異なる展開のトラブルをこどもから聞かされた保護者は、そりゃいい気持ちになりませんし、たいていは翌日や機会があるころに持ち出されてもはや修復不可能な事態に陥ってしまいます。ですから、気づかなかったならそれはそれでどうしようもないですが、気づいたことについては「すぐに」情報を保護者と共有しましょう。
そして「丁寧に」ですね。こども同士のトラブルにおいては児童クラブはどちらかの肩を持つ、味方をする、ということはしてはなりません。双方に丁寧に、トラブルを起こした側も、巻き込まれてしまった側にも、同じように差を付けずに対応しましょう。まして、児童クラブ側に非があって何か起こしてしまったのならなおのこと。「自分が仮に、相手の立場だったら、どう思うかな」ということを頭の中で想定してください。
保護者とやりとりするにあたって、かつてのような「職員と保護者が、お互いに顔が見える関係」ではなくなっている児童クラブもきっと多いでしょうし、もはや多数派なのでしょう。サービスを提供する側の児童クラブ職員と、カネを払った分のサービスはきっちり受けることを当然とする利用者たる保護者との間では、互いの「人間関係」がないので、トラブルをきっかけに厳しい対立関係に陥ることがごく普通にあります。それが、保護者によって社会通念上とても理解できないほどの圧がかかってくると、カスタマーハラスメントとなります。児童クラブはこのカスハラに悩まされている面が多いのですが、児童クラブ側も同時に、「こどもが人質にとられているようなものだから、改善を期待したいことがあってもなかなか職員には話せない。何か改善を要求したらクレーマーと思われてこどもが意地悪されるかもしれない」と内心、びくびくしている保護者が案外と多いことにも、留意しなければなりませんよ。
「そんなことないです。どんなことでも気軽に相談してください」と児童クラブ側はよく伝えますが、それはまず先に児童クラブの職員(運営も)側が率先して実行するべきなのです。
この部分を地道に取り組んでいると、トラブルがあったときの伝え方も、予想した最悪の展開にまで至らずに「今日は帰りが夜9時コースかと思ったら、あっさり5分で終わった!」となるのです。
<その79:児童クラブの保護者から職員には、「保護者ができる限り質問して!」が理想です>
夕方や夜になってこどもを迎えに来る保護者は、そりゃ忙しいです。夏休みなどの朝に児童クラブにこどもを連れていく場合はなおさら。出勤時刻に間に合うかどうか冷や冷やしている保護者さんもいるでしょう。時間が無いのは分かりますが、運営支援からのお願いです。1分2分でいいので、児童クラブの職員と会話をする時間をなるべく作ってください。そして「うちの子、どんなふうに過ごしていますか?」と尋ねてほしいのです。
ごく普通の児童クラブ職員でしたら、それはもう、満面の笑みで「実はですね、こうなんですよ!」と、いろいろと話をし始めるでしょう。だって、児童クラブの職員は、こどものことを、伝えたくて伝えたくて、うずうずしているんですから。こどもたちが成長すること、いままでできなかったことができたこと、あるいはいままでできていたことができなくなったということも含めて、保護者よりも、こどもの成長の「気づき」はたくさん持っているのが、児童クラブの職員です。だってこどもの成長を支えることが仕事なんですからね。
こどもが成長していく過程、あるいは困っていることも含めて、クラブの職員は、保護者のあなたに、たくさん伝えたくてうずうずしているんです。ですから、職員と話をする時間を頑張ってこしらえてほしいのですね。
先にも記しましたが「こどもが人質だから」と内心思っている保護者は、案外といます。わたくしも大勢、出会ってきました。一緒に保護者運営で児童クラブ職員と協力してきた仲間だと思っていた保護者ですら、そのようなことを口にした場面にでくわしたことだってあります。「ちょいとおまいさん、そんなふうに学童の先生のことを見ていたんかいな~」とびっくりしました。
でも、それが普通かもしれません。確かに、児童クラブの職員のひどい問題行動が報道されると、そんな気になってしまうかもしれませんね。ですが、多くの児童クラブの職員って、素朴なぐらい真面目で純粋で(だからこそバカ正直に)こどもに向き合っているので、親にひどいことを言われたからってこどもに仕返しをしてやろう、とは思う人は、まずめったにいないですよ。そりゃ日本全国何万人以上の児童クラブ職員がいますから、とんでもない人がいるかもしれませんが、それはどんな仕事だって同じ。あけすけに申せば、いつも児童クラブに対して根拠のない悪口しか言ってこない保護者を相手にしていても、そんな親のこどもに対してはむしろ「クラブにいるときは誰も人のことを悪く言わないから、思いっきり楽しんで過ごしなさいな」とすら思うものです。
気になることだってなんでもいいんですよ。「なんであの先生、いつも変な恰好なんですか?」でもいいんです。保護者はどんどん気になることがあったら児童クラブの職員に質問してください。もし、ルールとして可能であるならば、迎えに行ったときに児童クラブ室内に上がって、こどもたちの様子をその目で見てください。冬場はブーツを脱ぐのが面倒で、室内に入るのは大変ですけれどね。(ですから児童クラブ側が玄関にイスを置くという工夫をするんですよ! それが丁寧な接遇というものです)
<その80:児童クラブの保護者から職員には、「お願いですから、小さなことでも評価してあげて」がさらなる理想です>
「なんで、仕事でしょう、無事にこどもが過ごせることに対してどうして保護者から職員を評価しなければならないんですか」とお叱りの言葉を受けることを承知で、伏してお願い申し上げます。保護者のみなさん、児童クラブの職員は仕事ですから当然にこどもの成長を支え、援助し、支援しています。保護者の子育てもまた同じように支えています。それが仕事なんですが、でも、職員も人の子、人間なのです。ちょっとでも頑張っているなぁと思ったら、遠慮なくというか、大げさでもいいので、評価してあげてください。褒めてください。
仕事なのですが、その仕事が割と世間から評価されていないのが児童クラブなんです。給料が低いのは補助金が安いからです。補助金が安いのは児童クラブの仕事に対する賃金の評価を国が低く見積もっているから。つまり評価が不十分なんです。それなのに、こどもの成長を支えるのが大好きだからと安月給で長時間労働の激務を、あえて選択している児童クラブ職員のなんと多いことか。
またこれはわたくし萩原の独断ですが、児童クラブの職員は素朴で純粋な人が多いのですが、中には、いわゆる自己肯定感があまり高くない人もいるんですね。「自分がこどものときに受けたようなことがないよう、今のこどもたちにはめいっぱい良くしてあげたい」という思いで児童クラブにて働くことを選ぶ人もいます。こどもが成長していく様子を一緒に体験できることで職員も自身の自己肯定感を遅ればせながら育てていく、というパターンも、わたくしは多く見てきました。
ですからぜひともお願いします。何か頑張っている職員がいたら、一言でいいんです。「先生の頑張りでこどもが楽しく過ごせたんですね。良かったです」と言っていただけると、職員はそれでもうその夜は、満たされた気持ちで眠ることができます。
褒めて職員を育ててください。もちろん、ダメなことをしたなら遠慮なくご指摘ください。ダメなものはダメですから。
<その81:児童クラブの保護者さんには「みんなが過ごす場」という意識を持ってください>
これからインフルエンザがどんどん流行する季節ですね。児童クラブは、大勢のこどもが、職員と一緒に過ごす場です。特に感染症は、一気に他の人に感染させてしまう恐れがあるので、怖いんです。ですから、自分のおこさんが具合が悪いときは、しっかりと休ませてください。無理やり学校に登校させたり、児童クラブに登所させたりしないように、これだけは運営支援、厳しく要望します。
だってね、「児童クラブで感染が拡大して、学校の学級閉鎖や学年閉鎖になったら、発症していないこどもの保護者も仕事を休まざるを得ない状況になるかもしれませんよ。そんな目に遭ったら困るでしょう」。
もうひとつ、「児童クラブで相次いで職員が感染したら、児童クラブで働く人が足りなくなって、臨時閉所してしまうかもしれませんよ」。
何より最大のことは、「こどもが感染症にかかって発症したら、大変ですよ。特にインフルエンザ脳症のような危険な感染症になったら命を落とすかもしれませんよ。こどもが苦しむような可能性を増すようなことは、絶対にやめましょう」ということです。
児童クラブを利用する保護者さんには、なるべく、「このクラブのこどもたちみんなのお母さん、お父さん」という意識を感じてほしいと運営支援は願います。そして同じ立場にいる保護者さんたちが困らないようにお互いに気配りをしてほしいなあと願います。それは、おやつ料金や利用料などの滞納においてもそう。おやつ料金を支払わない家庭がいても、その家庭のこどもにだけ、クラブがおやつを出さないということはできません。そんなことをしたら格好のいじめ、からかいの対象になります。おやつは単に楽しみだけではなくて補食といって栄養面や活力の補給という大事な役割を持っています。おやつ料金未納の人の家庭のこどももおやつを食べるとなると、それが続けば、おやつの予算が減ったことでおやつの中身に影響が出てしまいます。結局は、みんなに影響が及ぶのです。何らかの事情で、今月の利用料やおやつ料金を支払えるだけの経済的な余裕が無い場合は、遠慮なく児童クラブの職員や運営本部、事務局に相談してください。そうです、どんなことでも相談してください。相談したからといって「はい免除です」とはなかなか、なりませんが、納入時期を延ばしてくれることや、何かしらの相談窓口に児童クラブ側が「つなぐ」ことができる可能性だってあります。
良くも悪くも「自分ひとりだけ」ではなかなか済まないのが、児童クラブです。大丈夫、児童クラブは子育てを支える仕組みでもありますから。遠慮なく相談してください。自分1人だけの行動が、みんなを巻き込むことになりがちなのですから、恥ずかしいことはありませんからね、ぜひ打ち明けてください。相談してくださいね。
※「トリセツ」シリーズは不定期に掲載しています。
第15回は2025年8月9日掲載でした。
<その61:なかなか職員の採用ができません。求人の応募がありません。どうすればいい?>
<その62:来てほしくない人が応募してくると大変面倒です。うまい手はありませんか>
<その63:児童クラブの仕事に向いている人が募集してくるような、巧い募集の文言はありますか?>
<その64:採用で、決して行ってはいけないことがありますか?>
<その65:採用に関して法令的に欠かせないことを教えてください>
第16回は2025年8月23日掲載でした。
<その66:ギュウギュウ詰めで困った!>
<その67:児童クラブに入れなくて困った!>
<その68:児童クラブで働いてくれる人が足りなくて困った!>
<その69:親が児童クラブに無理やり行かせるので困った!>
<その70:児童クラブの利用を始めた親なんですが、もっと忙しくなって困った!>
第17回は2025年9月20日掲載でした。
<その71:そもそも児童クラブの公立とか民間って何?>
<その72:公営、民営の区別を押さえておこう>
<その73:公立学童とは? 民間学童とは?>
<その74:利用料が高くなる原因は?>
<その75:公設公営、公設民営、民設民営、民間学童保育所、それぞれの特徴>
(お知らせ)
<社会保険労務士事務所を開設しました!>
2025年9月1日付で、わたくし萩原が社会保険労務士となり、同日に「あい和社会保険労務士事務所」を開業しました。放課後児童クラブ(学童保育所)を中心に中小企業の労務サポートを主に手掛けて参ります。なお、放課後児童クラブ(学童保育所)に関して、労働関係の法令や労務管理に関すること、事業に関わるリスクマネジメント、生産性向上に関すること、そしていわゆる日本版DBS制度に関しては、「あい和社会保険労務士事務所」を窓口にして相談や業務の依頼をお受けいたします。「あい和社会保険労務士事務所」HP(https://aiwagakudou.com/aiwa-sr-office/)内の「問い合わせフォーム」から、ご連絡のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
☆
「一般社団法人あい和学童クラブ運営法人」は、引き続き、放課後児童クラブ(学童保育所)の一般的なお困りごとや相談ごとを承ります。児童クラブの有識者として相談したいこと、話を聞いてほしいことがございましたら、「あい和学童クラブ運営法人」の問い合わせフォームからご連絡ください。子育て支援と児童クラブ・学童保育の運営者の方、そして行政の子育て支援と児童クラブ・学童保育担当者の方、議員の方々、ぜひとも子どもたちの安全と安心を守る場所づくりのために、一緒に考えていきましょう。セミナー、勉強会の講師にぜひお声がけください。個別の事業者運営の支援、フォローも可能です、ぜひご相談ください。
☆
(ここまで、このブログをお読みいただきありがとうございました。少しでも共感できる部分がありましたら、ツイッターで萩原和也のフォローをお願いします。フェイスブックのあい和学童クラブ運営法人のページのフォロワーになっていただけますと、この上ない幸いです。よろしくお願いいたします。ご意見ご感想も、お問合せフォームからお寄せください。出典が明記されていれば引用は自由になさってください。)