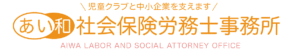採点するのが全員、身内って? 放課後児童クラブ(学童保育所)の運営事業者を決める仕組みに議員はもっと関心を!
放課後児童クラブ(いわゆる学童保育所)運営者をサポートする「運営支援」を行っている「あい和学童クラブ運営法人」代表の萩原和也です。放課後児童クラブを舞台に、新人職員の苦闘と成長、保護者の子育ての現実を描く、成長ストーリーであり人間ドラマ小説「がくどう、 序」が、アマゾン (https://amzn.asia/d/3r2KIzc)で発売中です。ぜひ手に取ってみてください! お読みいただけたら、アマゾンの販売ページに星を付けていただけますでしょうか。そして感想をネットやSNSに投稿してください! 最終目標は映像化です。学童の世界をもっと世間に知らせたい、それだけが願いです。ぜひドラマ、映画、漫画にしてください!
放課後児童クラブの運営事業者を決める仕組みはいろいろありますが、ごく普通に行われるようになっているのが公募による選定です。今回は、公募で児童クラブの運営事業者を決める仕組みに、もっと地域の政治家つまり議員が関心を持ってほしいと訴えます。同時に、国であれ地方自治であれ、議員政治家に児童クラブ支援の観点で期待したいことを紹介します。
(※基本的に運営支援ブログと社労士ブログでは、学童保育所について「放課後児童クラブ」(略して児童クラブ、クラブ)と記載しています。放課後児童クラブは、いわゆる学童保育所と、おおむね同じです。)
<児童クラブの運営事業者を決める、とは?>
放課後児童クラブは「放課後児童健全育成事業」を行っている施設のことです。学童保育所と呼ばれたり留守家庭育成室などいろいろな名称で呼ばれたりしていることは何度も運営支援ブログで紹介しています。
その、放課後児童健全育成事業は、児童福祉法という法律によって、市町村(以下「市区町村」と書きます。)が行うことができる「事業」とされています。つまり、市区町村は、放課後児童健全育成事業を行うことができますが、同時にこの法律では、放課後児童健全育成事業を民間が行うこともできると、定められています。つまり、児童クラブそのものである放課後児童健全育成事業というのは、市区町村というお役所と、民間つまり会社やNPO法人といった法人組織、保護者会や運営委員会という任意団体、また個人であっても、行うことができるのですね。
ところで事業を行うということをちょっとだけ整理しますと、「事業を行う場所や施設」と「事業の中身そのもの」に分けることができます。児童クラブでいえば、〇〇児童クラブという建物や施設そのもの、そしてその建物や施設で職員たちによって行われる育成支援、ということになりますね。つまり、施設を設置するという観点と、事業を行う=運営する、という観点の2つで、区別して考えることができるのです。その観点からよく使われているのが「公設公営」、「公設民営」、「民設民営」という3種類の児童クラブの分類方法です。
公設公営というのは、「市区町村等が設置した施設で、市区町村等が運営する」児童クラブ。
公設民営というのは、「市区町村等が設置した施設で、民間が運営する」児童クラブ。
民設民営というのは、「民間が設置した施設で、民間が運営する」児童クラブ。
(市区町村等の「等」が気になった方へ。珍しい例ですが地方公共団体となる組合による「組合立」クラブもありますので)
さて、運営事業者を決めるというテーマに戻りましょう。「公設民営」というパターンにおいて、「どの民間に、児童クラブの運営を任せようか」と市区町村が決める過程において、「運営事業者を決める」行為が必要となりますね。(民設民営にも実は「決める」行為が必要で、実はこれから書くことと同じだと考えて問題ありませんが、民設民営の場合には補助金が交付されている場合に限ります。)
これは実は児童クラブに限ったことではなくて、道路工事はじめいわゆる「公共工事」「公共事業」に関して、どの民間の会社や組織、つまり民間事業者に工事を任せるかを決めることもまた本質的に同じです。どうやって事業者を決めるのか話題になったのが2025年春から夏になって話題になった「備蓄米」騒動です。入札とか随意契約とか、いろいろな単語がニュースで飛び交いました。まったく同じことです。
児童クラブの運営をどの事業者に任せるか、大きく分けると「我々市区町村の立場からして、ぜひともやってほしい事業者さんと、直に交渉しますね」という「随意契約」と、「児童クラブ運営をしたい事業者さんからそれぞれ運営プランを提案してもらって、一番優れた内容の事業者さんに決めますね」という競争入札があります。この競争入札にはまた種類があって、単純に一番安い値段で引き受けると提案した業者に決める「一般競争入札」と、過去の実績などを踏まえて事前に市区町村が指名した事業者が参加して内容を競う「指名競争入札」と、前提条件さえクリアすればどの事業者でも参加できて、さらに単純に一番安い値段を提示した事業者ではなくて提案内容の全体を見て優れた内容の提案をした事業者を決める「企画競争入札」というものに分けられます。
児童クラブの運営事業者を市区町村が決めるときには、随意契約と、「企画競争入札」が多いように運営支援には見受けられます。この企画競争入札が「公募型プロポーザル」と呼ばれるものです。
(なお、どのような形態で運営を任せるか、という観点では「業務委託」「指定管理者制度」「事業への補助」という3形態があります。公募型プロポーザルは業務委託において用いられます。指定管理者制度を使って児童クラブ運営事業者を決める場合は、指定管理者選定委員会(名称は様々)という第三者機関が指定管理者の「候補事業者」を選び、それが市区町村の議会で決定されるという流れですが、その選定委員会で候補事業者を選ぶ際は、おおむね、立候補した事業者が提案する内容で最も優れた内容の事業者を決めるということになっているので、中身は公募型プロポーザルと同じようなものです)
ここまで読んでくださってよくわからなくなった方へ、つまりこういうことです。
「児童クラブを民間の組織が運営する場合は、市区町村が運営する事業者を決める。その決め方でよく使われるのは、「公募型プロポーザル」といって、提案内容を総合的に判断して最も優れた児童クラブ運営ができそうな事業者を選ぶスタイル。もう実績が十分でわざわざ競争相手と競わせる必要が無い場合は決め打ちで事業者を直接選んじゃう。それは随意契約、と呼ぶのです」
<公募型プロポーザルでも、これはどうなの?>
本日の運営支援ブログのもっとも言いたいことは、「公募型プロポーザルで児童クラブを運営する事業者を選ぶのは良いですよ。でも、選ぶ人たちのメンツ、メンバーが、全員、お役所の内部で固めているってのは、ちょっとおかしくない?」ということです。
児童クラブの本質は放課後児童健全育成事業ですが、その事業をどの会社、組織に任せるかを決めるのは市区町村です。ですから市区町村がどのように決めようかその判断に対して、私のような在野のローンウルフ(一匹狼)がいくら吠えようと何ら影響を及ぼせないのですが、地方自治は「二元代表制」といいますね、つまり「議会、議員」であれば、市区町村(=現実には「行政執行部」と称される、首長(=市長、町長、村長)に指揮される役所の機能そのもの)に対して、「それは、どうなの? 大丈夫なの?」と、疑問を呈したり、根拠をただしたりすることができます。
地方自治の議会、議員には、ぜひとも、行政執行部にずばりと聞いてほしいのです。「児童クラブの事業者を公募型プロポーザルで選ぶのは良いとしても、その審査委員のメンバーがすべて役所の内部の人物で占められることに、問題はないのか?」と。
例えばつい最近、公募型プロポーザルで広域展開事業者に児童クラブ運営を任せるようになった市があります。公募型プロポーザルの資料を終了後もホームページで公開していることは素晴らしい(すぐに非公開にする自治体があまりにも多すぎるので)のですが、そのせいでといえばそうですが、審査委員会のメンバーも公開されています。全5名の委員会メンバーのうち、市のナンバー2が委員長で、以下、部長や課長でメンバーが占められているのです。
「確かに行政の事業を誰に任すかを決めるので、市の偉い人がメンバーになるのは分かるけれど、全員?」というのがわたくし(萩原)の感想です。そうですねファーストガンダムに例えれば「ぜ、全滅? 12機のリック・ドムが全滅?」というコンスコン並みの信じられない思いですね。
違う自治体もあります。北海道旭川市も児童クラブ運営業務委託に係る公募型プロポーザル審査会委員名簿を公表していますが、全7名のうち行政担当者は2名で、残る5名が「外部委員」、しかも外部委員のうち2名が「学識経験者」となっています。運営支援も「そうだよね、そうでなければならないよね」と全同意です。
いま、公営の児童クラブの民間委託や、民間委託であっても保護者運営系のクラブが企業・法人運営系の児童クラブに「運営替え」するために公募型プロポーザルの実施や、指定管理者選定委員会が公募で事業者を募ることが増えています。その際に、議員は委員会や一般質問の場で、行政執行部が決めた審査委員や指定管理者選定委員会のメンバー構成にぜひとも注目して、そのメンバーになった根拠について行政執行部の理由を明らかにしてほしいのですね。
まして、児童クラブというのは、なかなか分かりにくい事業です。形態も、運営スタイルも、理念そのものも正確な知識や理解が広まっているとはいえない事業です。だからこそ、「どの事業者に任せるのが一番良いのか」を決めるメンバーには、旭川市のように外部からの視点を加えて選ぶこと、学識経験者に入ってもらうことが「必要」であると、運営支援は言い切ります。地方自治の議員は当然、国会議員も国会の場で、こども家庭庁の意見をただしてください。「児童クラブのことをあまり知らないと思われるメンバーだけで選ばれた児童クラブが増えることは、費用の有効な活用には結びつかないのではないのですか? 質の高い育成支援を実施するうえで妨げになる懸念はありませんか?」と。
ぜひ、議員、政治家には、公募型プロポーザルや指定管理者選定委員会に関して正しくその目的を発揮できるかどうか、監視をお願いしたいのですね。だいたい、行政ナンバー2という立場は一般的に役人のトップ(首長は政治家ですからね)であって、予算の元締めです。金食い虫である児童クラブの費用膨張に好意的な目を持っているとはなかなか想像しづらい。そういう役人のトップが委員長で、その他の委員が部下である部長や課長で占められた審査委員会が、児童クラブの質の高い運営を実現することの提案内容の趣旨が理解できるかどうか、重要視するかどうか、運営支援には極めて不安でしかありません。
<他にもある、議員、政治家の役割>
議員、政治家には、児童クラブの運営事業者を選ぶ局面や運営の形態を変更する局面だけに注目してくれればよい、ということでは全くありません。普段から、どんどん、児童クラブのことを議会、国会で取り上げていただきたい。
運営支援ブログでも、報道された議会での動きはチェックしています。例えば、さいたま市議会でいわゆる全児童対策事業の事業者がスポットワーカー(スキマバイト)を利用していたことを議員が追及したことや、奈良県香芝市で広域展開事業者が夏休みの間、人手不足を理由に1日もこどもに外遊びをさせなかったことなど、議会の場で児童クラブの問題点を指摘したことがあれば、運営支援ブログでも改めて取り上げています。
議員や政治家に期待したいことを列記して本日のブログを終わりとします。
・児童クラブの運営事業者を決める過程を監視し、行政執行部の企図を説明させる。
→本日のブログでは審査委員のメンバーに疑義を呈しましたが、もう1つ大事なことがあります。それは「審査表」「配点基準」です。こどもへの育成支援の充実に最も高い配点がなされているか、地域に根差した児童クラブがあったとしてその事業実績を正当に反映できる審査基準が盛り込まれているかどうか、審査表や審査基準、配点基準について議会の場でただすこと、理想的な審査基準を提案することが必要です。単に事業者の規模や他の地域での実績にそれなりの配点がされている審査基準は地元の事業者を不利に陥れます。
・クラブ(正確には「支援の単位」)ごとの収支を明らかにするよう行政執行部に求める。
→特に民間事業者のうち広域展開事業者が放課後児童健全育成事業の実態に費用を投じず事業者の利益計上にどれだけ収入を充てているかを監視するため。放課後児童健全育成事業をまっとうに行ったうえで余った剰余分を利益計上するのは全く問題ないですが、先に利益計上をして残った予算で事業を営むのは、本末転倒であり許されません。そうなっていないかどうかの監視は議会、議員の役割です。
・クラブで働いている職員の雇用労働条件がどうなっているか、議会の場で行政姓執行部から報告させる。
→正規(常勤)職員の月給がいくらか、時給換算額でいくらか、ということを毎年、明らかにさせましょう。児童クラブの職員はおしなべてワーキングプア状態です。
・最低賃金の急激な引き上げに児童クラブ事業者が対応できるよう行政執行部がどのような支援を行っているかを説明させる。
→最低賃金引き上げは素晴らしいことですが、国や自治体からの補助金が収入の多くを占める児童クラブは職員の賃金の原資となる補助金が増えなければ、最低賃金上昇分における賃金増加分を得ることが困難です。行政執行部の機敏な措置が必要であり児童クラブ事業者単独では対応が困難なことを、議会の場でしっかりと説明して行政執行部の対応を求めるべきでしょう。
・保護者の負担、とりわけ「経済的負担」と「運営負担」の2点に関する行政執行部の認識を明らかにさせる。
→国は児童クラブの運営にかかる費用の半分を保護者が負担するように、との考え方を示しています。この国の方針がそもそも「次元の異なる少子化対策」が求められる時代において正しいのか、議員は行政の方針をただすべきでしょう。保護者が児童クラブに支払う料金は、必要に迫られて支払う「子育て税」に等しいと運営支援はかねて訴えていますが、保護者の経済的負担の軽減は子育ての充実に欠かせません。同時に、いまなお保護者が児童クラブの運営を行う形態においては、保護者が運営に関する法的責任を負わされていることになりますが、実はその点を認識せずに長年の伝統だからと保護者が運営している児童クラブがとても多い。こども、職員の権利や安全を守るためには事業体としてしっかり整っていることが求められます。つまり「ちゃんとした会社や法人」が必要です。保護者運営のスタイルはもう時代にそぐわないことを行政執行部に説明することもまた議員の役割です。保護者運営が大事にしてきた「理念」を受け継いだ、事業体として整った事業者に児童クラブの運営を委ねればいいだけの話です。
・児童クラブで、こどもたちがどのように過ごしているのか行政執行部の認識を明らかにさせる。
→大規模状態の放置を許さない姿勢です。こどもが生活、成長する場の環境が劣悪であってはなりません。待機児童を生じさせないことは大前提ですが、見過ごされがちな大規模問題こそ議会で継続的に取り上げる課題です。
(お知らせ)
<社会保険労務士事務所を開設しました!>
2025年9月1日付で、わたくし萩原が社会保険労務士となり、同日に「あい和社会保険労務士事務所」を開業しました。放課後児童クラブ(学童保育所)を中心に中小企業の労務サポートを主に手掛けて参ります。なお、放課後児童クラブ(学童保育所)に関して、労働関係の法令や労務管理に関すること、事業に関わるリスクマネジメント、生産性向上に関すること、そしていわゆる日本版DBS制度に関しては、「あい和社会保険労務士事務所」を窓口にして相談や業務の依頼をお受けいたします。「あい和社会保険労務士事務所」HP(https://aiwagakudou.com/aiwa-sr-office/)内の「問い合わせフォーム」から、ご連絡のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
☆
「一般社団法人あい和学童クラブ運営法人」は、引き続き、放課後児童クラブ(学童保育所)の一般的なお困りごとや相談ごとを承ります。児童クラブの有識者として相談したいこと、話を聞いてほしいことがございましたら、「あい和学童クラブ運営法人」の問い合わせフォームからご連絡ください。子育て支援と児童クラブ・学童保育の運営者の方、そして行政の子育て支援と児童クラブ・学童保育担当者の方、議員の方々、ぜひとも子どもたちの安全と安心を守る場所づくりのために、一緒に考えていきましょう。セミナー、勉強会の講師にぜひお声がけください。個別の事業者運営の支援、フォローも可能です、ぜひご相談ください。
☆
(ここまで、このブログをお読みいただきありがとうございました。少しでも共感できる部分がありましたら、ツイッターで萩原和也のフォローをお願いします。フェイスブックのあい和学童クラブ運営法人のページのフォロワーになっていただけますと、この上ない幸いです。よろしくお願いいたします。ご意見ご感想も、お問合せフォームからお寄せください。出典が明記されていれば引用は自由になさってください。)