放課後児童クラブに、協働の可能性を見出そう。「協働のまちづくりセミナー」で、お話してきました。
放課後児童クラブ(学童保育)運営者をサポートする「あい和学童クラブ運営法人」代表の萩原和也です。放課後児童クラブ(いわゆる学童保育所)は子育て支援の大事な社会インフラですが、私は、社会資源としての児童クラブはその可能性をもっと広げられるはずだと考え続けています。本日(2025年1月31日)はその視点でお話をする機会を賜りました。ご紹介します。
(※基本的に運営支援ブログでは、学童保育所について「放課後児童クラブ」(略して児童クラブ、クラブ)と記載しています。放課後児童クラブはおおむね学童保育所と同じです。)
<栃木県栃木市からお声がけいただきました>
栃木県栃木市は、人口で県内第3位、歴史ある蔵の街とのことで小江戸として、あの川越市と並ぶ称される、とても風情のある地域です。栃木・群馬・埼玉の3県の県境があるというのは、地理好きには興味深いですね。その、栃木市の「とちぎ市民活動推進センター くらら」さんから、「学童保育を視点にした、協働についてぜひお話いただけないか」というお話を頂戴しました。
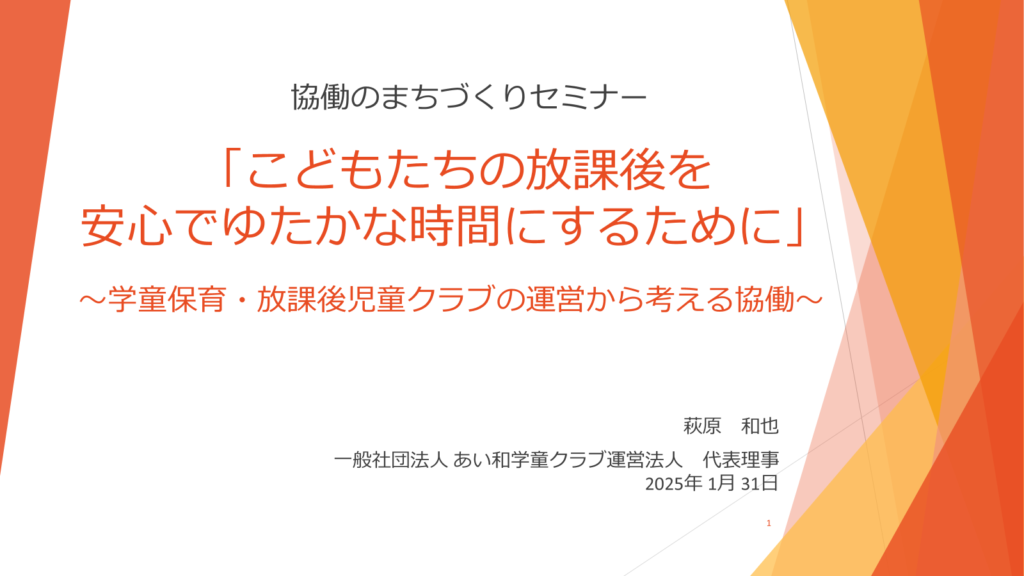
私は常々、放課後児童クラブは地域社会、自治体とともに発展していくことができる社会資源であるはず、という考えを持ってきました。実際、実務で児童クラブの運営事業者の長を務めていたときは、その考えでいろいろな活動計画も考えてきました。運営支援という視点において、児童クラブが地域社会にしっかりと「組み込まれて」、地域社会および自治体の発展に寄与することは、児童クラブの持続的かつ安定的な事業運営を担保する意味でも、とても重要なことと捉えています。その視点で、お話をする機会を賜れたことはとても光栄ですし、その視点を持って児童クラブの今後を考えたいと思われた栃木市さんには、本当に先見の明があると私は感じた次第です。
どのような内容をお伝えしたのかは、下の要旨をごらんいただければあらかた想像はつくでしょう。
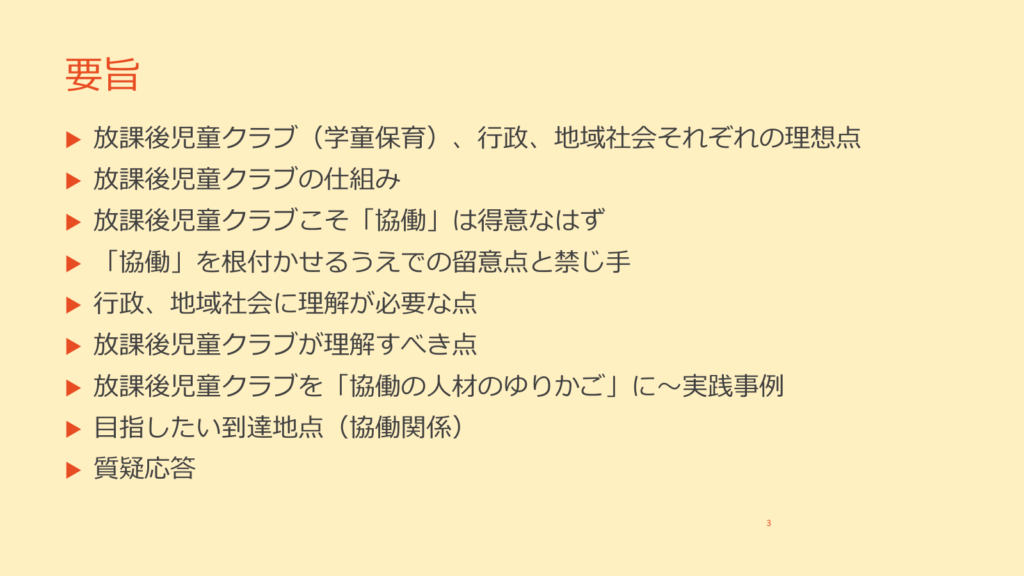
放課後児童クラブの大きな流れの中でも、児童クラブにおける子どもの過ごし方、子どもの育ちを、保護者と職員が一緒に考えていくスタイルがあります。保護者運営はそのものずばりですが、保護者運営から発展した法人による児童クラブ運営もまた、児童クラブを利用する保護者たちが、一緒に話して考える機会を得ることができます。
または、強制的に、保護者たちが否応なく、児童クラブの運営について業務、作業をせざるを得ない形態があります。この場合は保護者がどんなに嫌でも、一緒に話して作業をしなければ児童クラブの運営ができませんから、必然的に、保護者同士、あるいは職員も加わっての共同作業を行うことになります。
こうした、保護者同士の関わり、結びつきによる作業こそ、「同じ目的を、他者と一緒になって実現していく」ことのまさに原点であって、これをじわじわと拡大していくことができれば、その活動は児童クラブの世界を超えて、地域社会に広げていくことができる、というのが私の持論です。そして本日のセミナーでもご説明した内容です。
強制的な保護者の運営従事について私は賛成はしていませんが、現実的にはまだまだ多く残っている以上、その問題点をできるだけ軽減しながら、保護者同士が一緒に話して考える機会を確保することが大切です。
特に力を入れて私なりに伝えたことが2点。
1つは、任意性のこと。やっぱり、無理やり参加させることは、かえってマイナスです。拒否感、嫌悪感だけを植え付けます。やりたい人が、やれることを行うというスタンスをずっと守っていくべきです。「子どものためだから」と押し付けるのは絶対にやめましょう。
もう1つは、結局のところ、どういう児童クラブにするか、どういう児童クラブになるかは、事業運営である以上、児童クラブを設置して補助金を交付している行政次第だ、ということです。それは、地域の子どもたちに、どういう育ちを保障するのかという、子どもの育ちのビジョンを明確化しているか、という点にまでさかのぼります。「児童クラブはしょせん預り場なのだから、とにかく、問題なく過ごしてさえくれればいいよ」となれば、あちこちで児童クラブを運営している企業、広域展開事業者による児童クラブが、しっかりとした運営スキームを確立しているだけに最適となります。ただしその分、すでに運営の仕組みが確立されているがゆえ、保護者があれこれと試行錯誤もしながら話し合って作り上げていくプロセスを「協働の面白さの気付き」として位置付けることができる可能性は、総じて低くなります。
一方で、他者とのつながり、それは実に面倒くさいものでもありますが、保護者同士の連携を育てていくということに価値観を見出していれば、保護者たちが児童クラブにおける子どもの育ちについて意見を述べ、職員とともに取り組むことができるスタイルの児童クラブ運営を選択することが最適です。どういう選択をするか、それは最終的に行政の判断です。補助金をどれだけ出すか決めるのも行政、どういう児童クラブが地域の子どもたちを支えていくのか決めるのも、やっぱり行政なのです。行政が児童クラブの命運を握っているのです。それは、何度も申し上げました。
あとは、児童クラブの職員の専門性、とりわけボランティア・コーディネーターとしての能力を身に着ける必要があるということですね。なにせ、今の多くの保護者は、もともと人間関係が希薄となっている地域社会で育っているがゆえ、仲よしや同じ学年の保護者以外の第三者、まして地域の方々と一緒に活動に取り組む機会をほとんど経ないまま、児童クラブの世界に足を踏み入れます。そこで、仮に、濃厚な保護者同士の関係が必要とされる世界に足を踏み入れてしまっては、戸惑うどころか、嫌々な気持ちがむくむくとわいてしまうことになりかねません。その点、児童クラブの職員が、他者と連携して活動することに興味を持たせるような活動を、保護者に「仕掛けていく」観点が必要でしょう。
児童クラブという場所で、子どもの安全安心な育ちを保障するという保護者であれば誰しも納得できる共通の命題のもとに、どうやったらより充実した児童クラブとすることができるか、保護者同士がアイデアを出し合って共に活動を重ねていく。そのことが、「一緒に活動することの楽しさ、充実感」を保護者たちに植え付け、協働という、なにやらとっつきにくい考え方がごく自然と身についていく。そうした保護者を児童クラブは作り出すことができます。保護者を、染めることができます。もちろん、全員がそうなるはずはありません。10人に1、2人でしょう。いや20人に1人ぐらいかもしれないですし、そんなものでしょう。それでいいんです。0人が1人、2人となれば、それだけで大収穫です。児童クラブで協働の考え方を知らず知らず身に着けた人が地域の活動に参加するようになり、地域が盛り上がっていくことになれば、それは児童クラブ、地域社会、そしてその自治体にも、利益があることなのです。
児童クラブは、地域を盛り立てる協働が好きな人を育てることができる、ゆりかごとしての機能をもっているのだと、私は感じているのです。
<お客様となった保護者をどうすれば?>
セミナーでは質問を頂戴しました。児童クラブの運営者の方からでした。キャンプに保護者が参加しても、積極的に動くことができず、お客様のようになってしまう。どうしたらいいでしょう、ということでした。「お客様化」ですね。まず、お客様になるのは当然だという前提があります。本来、児童クラブにおいて、子どもとその監護者は、児童の健全育成事業という公的な事業のサービスを受ける側にあります。サービスを受けてその対価を支払う者を客と表現するなら、児童クラブの保護者は客です。
もちろん質問された方はそれを承知の上で、「協働のささやかな第一歩となる、児童クラブにおける共同作業をどうしたら保護者さんが積極的参加できるようになるか」ということをお尋ねになりたかったのです。
私は次のように考えます。
キャンプというのは、今の保護者にとってかなりハードルが高いのです。キャンプが好きで家庭で行っているという人でも管理キャンプ場でそれなりに整った状況でのキャンプをします。また、家族や気の置けない仲間だけで行くキャンプは勝手気ままに作業ができます。それと、本質的には赤の他人に近い人たちと一緒に過ごす学童キャンプは異なります。そういうキャンプで求められる経験や気配りは、それまで積んできた親しい仲間内での範囲の世界の経験値で到底補えるものではありません。
「もっと小さなことからスタートした方が良いでしょう」とお答えしました。実際は、サービスを受ける側に回っていても最初のうちはいいんです。「一緒に食べる、一緒に過ごす」ことからスタートです。私が例に挙げたのは、児童クラブの保護者会が終わって、そこでみんなでカレーライスや、焼きそばを食べる経験を積むこと、でした。多くの人が、食べるだけでいいんです。その作業の中で、自然と、紙皿を整えたり、盛り付けをしたり、ごみ片づけをしたりして、「同じ場で、何らかの行動をして、一緒に食べる、一緒に片づける、という目的に向かってそれぞれが別々の作業をする」、それがまさに協働のスタートだからです。そのうち、「じゃあ次は私が、から揚げを作って持ってくるよ」となるかもしれません。「サンドイッチを持ってくるね」となるかもしれません。
いきなりキャンプより、ちっちゃな共同作業でいいんです。「それ、サービスを受けているだけじゃないの」でいいんです。あるいは保護者会の場で、子どもの宿題や動画視聴、お小遣い、ゲームについて小グループで自由に意見交換をする。その経験を積み重ねていくと、最初はなかなか意見を披露できなかった人も「場慣れ」して「実は、ウチではこんなことが」という話ができるようになるものです。
児童クラブのキャンプ、学童キャンプについて私は一家言持っていますが、キャンプ好きな人、学童キャンプが大好きな人ほど、「あれほど楽しいんだからやってみればわかるって」となります。それは違うのです。今の時代、キャンプそのものに魅力を感じる人はそれほどいません。ソロキャン、ゆるキャンのように細分化もしています。自分(たち)のレベルで推し量っては失敗します。アウトドア活動はその傾向が顕著だと私は考えます。
「小さく生んで、大きく育てる」の意識で、時間はかかりますが、じっくりと協働が大好きな人を見出していきましょう。育てていきましょう。それが毎年続けば、地域の大きな財産となるのですから。
セミナー講演の終盤には、新潟市の「岩室地域児童館」で行った「じどうかん運動会」について、時間を割いてご紹介しました。児童クラブではないですが、子育て支援の施設として児童クラブと同等に重要な役割を果たしている児童館が、地域との交流、協働を目指して活動に取り組み、成功裏に進んでいる好事例として紹介いたしました。情報をご提供いただいた川邊素子館長には本当に感謝しております。
ぜひ、いろいろな地域の方も、児童クラブを活かしたまちづくり、人材づくりについて考えてみませんか? お声がけいただければ、私はどこへでも駆けつけます。(交通費と、お出しいただける範囲で全くかまいませんから謝礼も、お願いします。)
<おわりに:PR>
弊会は、次の点を大事に日々の活動に取り組んでいます。
(1)放課後児童クラブで働く職員、従事者の雇用労働条件の改善。「学童で働いた、安心して家庭をもうけて子どもも育てられる」を実現することです。
(2)子どもが児童クラブでその最善の利益を保障されて過ごすこと。そのためにこそ、質の高い人材が児童クラブで働くことが必要で、それには雇用労働条件が改善されることが不可欠です。
(3)保護者が安心して子育てと仕事や介護、育児、看護などができるために便利な放課後児童クラブを増やすこと。保護者が時々、リラックスして休息するために子どもを児童クラブに行かせてもいいのです。保護者の健康で安定した生活を支える児童クラブが増えてほしいと願います。
(4)地域社会の発展に尽くす放課後児童クラブを実現すること。市区町村にとって、人口の安定や地域社会の維持のために必要な子育て支援。その中核的な存在として児童クラブを活用することを提言しています。
(5)豊かな社会、国力の安定のために必要な児童クラブが増えることを目指します。人々が安心して過ごせる社会インフラとしての放課後児童クラブが充実すれば、社会が安定します。経済や文化的な活動も安心して子育て世帯が取り組めます。それは社会の安定となり、ひいては国家の安定、国力の増進にもつながるでしょう。
放課後児童クラブ(学童保育所)の運営支援は、こどもまんなか社会に欠かせない児童クラブを応援しています。
☆
弊会代表萩原ですが、2024年に行われた第56回社会保険労務士試験に合格しました。これから所定の研修を経て2025年秋に社会保険労務士として登録を目指します。登録の暁には、「日本で最も放課後児童クラブに詳しい社会保険労務士」として活動できるよう精進して参ります。皆様にはぜひお気軽にご依頼、ご用命ください。また、今時点でも、児童クラブにおける制度の説明や児童クラブにおける労務管理についての講演、セミナー、アドバイスが可能です。ぜひご検討ください。
☆
放課後児童クラブについて、萩原なりの意見をまとめた本が、2024年7月20日に寿郎社(札幌市)さんから出版されました。本のタイトルは、「知られざる〈学童保育〉の世界 問題だらけの社会インフラ」です。(わたしの目を通してみてきた)児童クラブの現実をありのままに伝え、苦労する職員、保護者、そして子どものことを伝えたく、私は本を書きました。学童に入って困らないためにどうすればいい? 小1の壁を回避する方法は?どうしたら低賃金から抜け出せる?難しい問題に私なりに答えを示している本です。それも、児童クラブがもっともっとよりよくなるために活動する「運営支援」の一つの手段です。どうかぜひ、1人でも多くの人に、本を手に取っていただきたいと願っております。注文はぜひ、萩原まで直接お寄せください。書店購入より1冊100円、お得に購入できます!大口注文、大歓迎です。どうかご検討ください。
☆
放課後児童クラブを舞台にした小説を完成させました。いまのところ、「がくどう、序」とタイトルを付けています。これは、埼玉県内の、とある町の学童保育所に就職した新人支援員が次々に出会う出来事、難問と、児童クラブに関わる人たちの人間模様を、なかなか世間に知られていない放課後児童クラブの運営の実態や制度を背景に描く小説です。新人職員の成長ストーリーであり、人間ドラマであり、児童クラブの制度の問題点を訴える社会性も備えた、ボリュームたっぷりの小説です。残念ながら、子ども達の生き生きと遊ぶ姿や様子を丹念に描いた作品ではありません。大人も放課後児童クラブで育っていくことをテーマにしていて、さらに児童クラブの運営の実態を描くテーマでの小説は、なかなかないのではないのでしょうか。児童クラブの運営に密接にかかわった筆者だからこそ描ける「学童小説」です。ドラマや映画、漫画の原作にも十分たえられる素材だと確信しています。ご期待ください。
☆
「あい和学童クラブ運営法人」は、学童保育の事業運営をサポートします。リスクマネジメント、クライシスコントロールの重要性をお伝え出来ます。子育て支援と学童保育の運営者の方、そして行政の子育て支援と学童保育担当者の方、議員の方々、ぜひとも子どもたちの安全と安心を守る場所づくりのために、一緒に考えていきましょう。セミナー、勉強会の講師にぜひお声がけください。個別の事業者運営の支援、フォローも可能です、ぜひご相談ください。
☆
(このブログをお読みいただきありがとうございました。少しでも共感できる部分がありましたら、ツイッターで萩原和也のフォローをお願いします。フェイスブックのあい和学童クラブ運営法人のページのフォロワーになっていただけますと、この上ない幸いです。よろしくお願いいたします。ご意見ご感想も、お問合せフォームからお寄せください。出典が明記されていれば引用は自由になさってください。)



