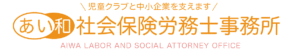介護しながら働く放課後児童クラブ(学童保育所)職員はいますし、今後も増えるでしょう。介護中の職員を支えよう!
※本日は<あい和社会保険労務士事務所>としての「児童クラブの社労士ブログ」です。
放課後児童クラブ(いわゆる学童保育所)運営事業者をサポートする「あい和社会保険労務士事務所」社会保険労務士の萩原和也です。
2025年10月1日から、育児・介護休業法の改正に伴って介護に関するいくつかの対応を事業者が実施することが義務となります。前日のブログ(2025年9月11日)では、育児をしながら働く職員を支える施策を紹介しました。今回は介護離職を防止するために導入された施策と、育児に関しても本年4月から施行されている施策を紹介します。
(※基本的に運営支援ブログ同様、「社労士ブログ」でも、学童保育所について「放課後児童クラブ」(略して児童クラブ、クラブ)と記載しています。放課後児童クラブはおおむね学童保育所と同じです。)
<介護離職防止のための個別の周知・意向確認>
これは、すでに2025年4月1日から実施することが義務になっているものです。児童クラブ事業者も、介護をしながら働く職員がいるでしょうし、急激な超高齢化社会の進展で今後はもっと増えるでしょう。児童クラブ事業者は、この項で紹介する施策を確実に実施するためのマニュアルの準備を勧めましょう。
この施策で事業者の義務となっていることを紹介します。児童クラブで働いている職員が、「介護に直面しています」という申し出をしてきたときに、事業者は、介護休業および介護両立支援制度等に関する、次に紹介する事項の「周知」と、制度利用の「意向確認」を行わなければならない、となっています。つまり「周知」と「意向確認」が必要です。前日のブログで紹介した育児に関することと同じ仕組みです。
対象者は、「介護に直面していることを申し出た職員(労働者)」です。
周知事項は、次の3つです。
①介護休業に関する制度、介護両立支援制度等
→介護両立支援制度等とは「介護休暇に関する制度/所定外労働の制限に関する制度/時間外労働の制限に関する制度/深夜業の制限に関する制度/介護のための所定労働時間の短縮等の措置、の5つです。
②介護休業と介護両立支援制度等の申出先
→児童クラブの事業者の、どの部署、誰が担当者なのかを知らせること
③介護休業給付に関すること
個別周知と、意向確認の方法は4通りです。面談、書面交付、ファクス、電子メール等、のいずれかですが、ファクスと電子メール等は、あくまで職員側が希望したときだけです。
これも前日のブログで記載しましたが、育児のときと同様、この介護に関する制度についても、個別周知と意向確認を事業者側が行う時に、休業や休暇の取得や制度の利用を職員が控えさせるような形で行ってはなりません。「誰も利用したことがないんだよね」とか「そういう制度はあることはあるけど、利用されちゃうと人が足りなくて困るんだよね」などと事業者側がほのめかしてはいけません。
<介護に直面する前の早い段階(40歳等)での両立支援制度等に関する情報提供>
これも「義務」で、すでに2025年4月1日から施行されています。この施策を分かりやすく言うと、職員が仕事と介護の両立支援制度を知らない職員が突然、介護に直面して仕事を辞めるようなことにならないために、40歳をめどに、介護休業および介護両立支援制度等に関する「情報提供」を、職員に行うこと、です。なぜ40歳がめどになっているかといえば、40歳になった人で健康保険または国民健康保険に加入している人は「介護保険料」を収めることになるからです。
この義務の内容を紹介します。
対象者と介護に関する情報提供の期間ですが、2パターンあります。「職員が40歳に達する日(=誕生日の前日)の属する年度(1年間)」と、「職員が40歳に達した日の翌日(=誕生日)から1年間」です。
なんだかよく分からないかもしれません。法律で、人間が年齢を重ねる、つまり39歳だった人が40歳になるのは、「誕生日の前日」と規定されています。つまりですね、4月1日生まれの人は、法律上、4月1日に40歳になるのではなくて前日の3月31日に40歳になるんです。ですから1970年4月1日生まれの人は1970年3月31日に年を重ねる、つまり「1969年度の人」になるんですね。そしてこれを言い換えると、「法律上、年を重ねた日の翌日が誕生日になる」ということです。
「属する年度」とは、該当する日がある年度のことです。4月1日が誕生日の人は、前日の3月31日に年を重ねますから、その3月31日がある年度が「属する年度」となります。1970年4月1日生まれの人は「1969年度」が属する年度、となります。
ですから、40歳になった人が4月1日生まれだとすると、その前日である3月31日の年度、誕生日を基準にすると「前年度」ですが、その年度と、誕生日である4月1日から1年間が、この義務の期間(=情報提供期間)、ということになります。
もっと訳が分からなくなりましたか? ざっくり言えば、「児童クラブで働いていて40歳になる職員がいる場合は、その職員が40歳になる年度と、誕生から1年後の間までに、説明してください」ってことです。2025年9月12日が誕生日で40歳になる職員がいるならば、「2025年4月1日から、2026年9月11日まで」の間に、介護休業とか介護休業給付、両立支援制度について事業者は職員に説明しなければなりませんよ、ってことです。
提供する情報は3つです。「介護休業に関する制度と介護両立支援制度等」、「介護休業、介護両立支援制度等の申出先(相談先窓口や担当者)」、そして「介護休業給付に関すること」です。情報提供については「面談」「書面交付」「ファクス」「電子メール等」のいずれかでOKです。
なお、「望ましい」こととして、「介護保険制度」に関しても、説明して周知することと、国は示しています。介護保険制度はとても難しいので、必要に応じて、専門知識を備えた人に説明をしてもらうことも良いでしょう。
<研修や相談窓口の設置等の雇用環境の整備>
これも10月1日からの義務です。児童クラブの事業者は、介護休業と介護両立支援制度等の「申出が円滑に行われるように」するため、次の「いずれかの措置」を講じなければなりません。
措置の内容は次の4つです。
① 介護休業・介護両立支援制度等に関する「研修の実施」
→少なくとも管理職は、研修を受けたことがある状態にしましょう。
② 介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備=相談窓口設置
→介護に直面する、あるいは将来の不安についても相談を受ける窓口や担当者を決めて全職員に周知しましょう。なお、育児に関しても同様の相談窓口の設置が義務となっていますが、育児と介護の双方を一緒に担当することは可能ですが、育児と介護の双方の窓口ですよ、担当者ですよ、ということは丁寧に確実に周知してください。
③ 自事業者の職員への介護休業・介護両立支援制度等の取得「事例の収集・提供」
→すでに実施した事例を職員に紹介しましょう。
④ 自事業者の職員への介護休業・介護両立支援制度等の制度及び「取得促進に関する方針の周知」
→事業者としてどのように介護休業・介護両立支援制度等を推進していくのか、組織の方針を職員に知らせることです。社内報や掲示物、職員であれば閲覧できるネット掲示板に掲載しましょう。
<その他>
育児・介護休業法の改正では介護についてもテレワークを選択できるような措置を事業者が講ずることが「努力義務」となっていますが、児童クラブの現場ではテレワークは導入がほぼ不可能ですので、これは仕方がないでしょう。
なお、「介護休暇」に関しては、以前の制度において労使協定によって「引き続き雇用された期間が6か月未満」の労働者は除外できるとなっていました。つまり採用したばかりの新人は対象外にできますよ、ということでしたが、今回の法改正でこの規定はなくなりました。つまり採用したばかりの新人が突然、介護に直面した場合でも介護休暇を取得できる、ということになります。注意しましょう。
ここからは、すでに2025年4月1日から施行されている、育児に関する制度の紹介です。結構難しい内容ですから、児童クラブ事業者におかれましては、顧問契約をしている社会保険労務士がいればその方に、そうでなければ十分に理解している社労士の人に依頼して、職員に説明してもらうことが望ましいです。カネと休みに関することなので、丁寧に対応しないと後日、「どうして知らせてくれなかったのか。損をした」と労使トラブルになる可能性もあります。
<育児休業給付の給付率引き上げ>
育児休業給付(=これ、こども家庭庁の予算です。こども家庭庁を無くせと気楽に言う人たちは、この制度を無くせと言っていることです。そんなバカげた主張は無視しましょう。ただその予算の原資は、社会保険料を納めている企業が支払っています)は、育児休業を取得した人に対して、休業開始から通算で180日間は賃金の67%、180日を過ぎると50%が支給されるものです。
今回の改正で、極めて短い期間ではありますが、こどもが生まれた直後の一定期間(男性はこどもの出生後8週間以内、女性は産後休業後の8週間以内)のうちに、夫婦の両方が14日以上の育児休業を取る場合に、最大28日間、さらに13%が上乗せされる、というものです。国は「これで手取り100%をカバーできる」としています。
なおこの制度は、配偶者が専業主婦(夫)や、ひとり親家庭の場合はそのまま給率が引き上げられることに注意が必要です。
なお、「望ましい」こととして、職員のこどもに障がいがある場合や、医療的ケアを必要とする場合には、職員が希望する場合、短時間勤務制度や、「子の看護等休暇等」(=次回以降、説明します)の利用可能期間を独自に延長することが挙げられています。また、ひとり親の場合は、「子の看護等休暇等」の付与日数を増やすなどの措置が望ましいと、されています。
これはとても難しいので、ベテラン社労士に相談することをお勧めします。
<育児時短就業給付>
新しくできた制度です。とても難しい制度ですから、専門家に説明を受けてください。簡単にいえば、「2歳未満の子を育てているため」に、「時短勤務をしている」人に対して、時短勤務のために以前より賃金が減った場合に、「時短勤務中に支払われた賃金額の10%」を国が支払いますよ、というものです。2025年4月1日から始まった制度ですが、その日より前にすでに育児による時短勤務をしている人も対象になります。
<残業免除の拡大>
これまでは、3歳になるまでの子を育てている職員であれば、所定外労働つまり残業をしないことを事業者に請求することができました。これが、3歳になるまでの子から、小学校就学前の子までのこどもを養育する職員に拡大されました。
(でもこれ、小学校に入っても必要ですよね。国はもっと本腰を入れてこの制度の充実を図っていただきたいですね)
ちなみに、3歳に満たないこどもを育てる労働者がテレワークを選択できるような措置を講ずることが、事業主の努力義務となりました。児童クラブはテレワークと極めて相性が悪い職種ですからほとんど恩恵はないでしょう。
<「子の看護等休暇」に発展>
これまでは「子の看護休暇」という制度がありました。こどもが小学校就学するまでの間に、「病気、けが」と「予防接種、健康診断」の場合に使える休暇の制度でした。
それが2025年4月1日から「子の看護等休暇」と「等」の文字が追加されました。なぜかといえば、休暇を取得できる事由に「感染症に伴う学級閉鎖等」が加わったこと、「入園(入学)式、卒園式」が追加されたからです。学級閉鎖については自分のこどもが感染していなくても、つまり健康でいても学級閉鎖で自宅待機しなければならない状態でも認められます。
ちょっと残念なのは入園入学式や卒園式です。そのときに使えるのはいいんですが、「式典」に限られるんですね。これ、PTAや学級懇談会などにも使えるようにさらに法改正が必要ですね。
そして、使える時期が拡大されました。「小学校3年生修了まで」に延長されました。これも評価できますが、どうせなら小学校修了までに拡大するべきでしょう。
そして最後、これも介護のときと同じように、労使協定によって、雇用されて6か月未満の職員を除外することが今まではできましたが、法改正によって除外できなくなりました。つまり児童クラブで採用して働き出した人も、この「子の看護等休暇」を利用できます。
なお、取得可能な休暇の日数は今まで通り、1年間に5日、子が2人以上の場合は10日で、変更ありません。
以上、紹介した制度も、小さな児童クラブ事業者ではなかなか完全にやり遂げるのは事実上、困難でしょう。そんなのは児童クラブを運営していた私も現実問題として理解しています。ですが、法は法、守らねばなりません。「できないから守れない」ではダメです。ですから小さな児童クラブ事業者は、介護に直面しても、小学生のこどもを育てながらでも児童クラブで働けるような態勢を整えるために、どんどん合流合併して、規模の大きな事業者となるべきです。そうすれば、こういう法令にも対応できるようになるのですから。それがひいては、育成支援の質の高い児童クラブを守り、児童クラブで働き続けたい職員に末永く勤務を続けてもらえる場所を準備することになるからです。どんどん合併、とっとと合併! ですよ。
(お知らせ)
<社会保険労務士事務所を開設しました!>
2025年9月1日付で、わたくし萩原が社会保険労務士となり、同日に「あい和社会保険労務士事務所」を開業しました。放課後児童クラブ(学童保育所)を中心に中小企業の労務サポートを主に手掛けて参ります。なお、放課後児童クラブ(学童保育所)に関して、労働関係の法令や労務管理に関すること、事業に関わるリスクマネジメント、生産性向上に関すること、そしていわゆる日本版DBS制度に関しては、「あい和社会保険労務士事務所」を窓口にして相談や業務の依頼をお受けいたします。「あい和社会保険労務士事務所」HP(https://aiwagakudou.com/aiwa-sr-office/)内の「問い合わせフォーム」から、ご連絡のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
「一般社団法人あい和学童クラブ運営法人」は、引き続き、放課後児童クラブ(学童保育所)の一般的なお困りごとや相談ごとを承ります。児童クラブの有識者として相談したいこと、話を聞いてほしいことがございましたら、「あい和学童クラブ運営法人」の問い合わせフォームからご連絡ください。子育て支援と児童クラブ・学童保育の運営者の方、そして行政の子育て支援と児童クラブ・学童保育担当者の方、議員の方々、ぜひとも子どもたちの安全と安心を守る場所づくりのために、一緒に考えていきましょう。セミナー、勉強会の講師にぜひお声がけください。個別の事業者運営の支援、フォローも可能です、ぜひご相談ください。
☆
(ここまで、このブログをお読みいただきありがとうございました。少しでも共感できる部分がありましたら、ツイッターで萩原和也のフォローをお願いします。フェイスブックのあい和学童クラブ運営法人のページのフォロワーになっていただけますと、この上ない幸いです。よろしくお願いいたします。ご意見ご感想も、お問合せフォームからお寄せください。出典が明記されていれば引用は自由になさってください。)