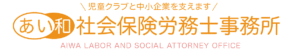「日本版DBS制度」の「中間とりまとめ」が公表されました。放課後児童クラブ(学童保育所)が今すぐ取り組むこと
放課後児童クラブ(いわゆる学童保育所)運営者をサポートする「運営支援」を行っている「あい和学童クラブ運営法人」代表の萩原和也です。放課後児童クラブを舞台に、新人職員の苦闘と成長、保護者の子育ての現実を描く、成長ストーリーであり人間ドラマ小説「がくどう、 序」が、アマゾン (https://amzn.asia/d/3r2KIzc)で発売中です。ぜひ手に取ってみてください! お読みいただけたら、アマゾンの販売ページに星を付けていただけますでしょうか。そして感想をネットやSNSに投稿してください! 最終目標は映像化です。学童の世界をもっと世間に知らせたい、それだけが願いです。ぜひドラマ、映画、漫画にしてください!
2026年12月から始まる、いわゆる「日本版DBS制度」について、こども家庭庁は2025年9月12日に「中間とりまとめ」を公表しました。この中間とりまとめは、日本版DBS制度がどのように実施されるのかを示しているものです。非常に膨大な情報量、かつ、とても難しい制度の内容です。今回の運営支援ブログでは、児童クラブの関係者とりわけ運営に関わる方々に向け、実務上、「これだけは今すぐ準備にとりかかってほしい」ことを紹介します。
(※基本的に運営支援ブログと社労士ブログでは、学童保育所について「放課後児童クラブ」(略して児童クラブ、クラブ)と記載しています。放課後児童クラブは、いわゆる学童保育所と、おおむね同じです。)
<認定事業者になるか、ならないか>
日本版DBS制度において放課後児童クラブは、その制度を受け入れるかどうかを選べます。保育所や放課後等デイサービスは、有無を言わせず日本版DBS制度は義務となるのですが児童クラブは選択の余地があります。つまり、日本版DBS制度を受け入れない、実施しない選択肢も、あります。
「わたしたちのクラブは、日本版DBS制度を受け入れるか、受け入れないか」を、もう決めましょう。
大事な観点があります。それは、「自分たち以外の立場の方々が、どう判断するか」です。つまり、日本版DBS制度を選ばないとした児童クラブに対して、利用者たる保護者や、放課後児童健全育成事業を業務委託している、または同事業を行う指定管理者として選んでいる、または同事業を行っていることに対して補助金を出している市区町村が、日本版DBS制度を選択しないと決めた児童クラブ事業者に対して、どのような評価、判断を下すのかという、「第三者から向けられる評価」を、常に考慮しておく必要がある、ということです。
それは例えばですが、「あの児童クラブは日本版DBS制度を選ばなかった。日本版DBS制度に対応しているという会社が児童クラブをやりたいと言ってきている。では、日本版DBS制度をやるとしている業者にこれから任せようか」と、自治体が判断する余地がありえる、ということです。
または、こどもをクラブに通わせている保護者から、「どうしてうちの児童クラブは、日本版DBS制度を適用するとしなかったのですか。もしかしたら、実は、過去に性犯罪の前科がある人が働いているからじゃないんですか? 説明してください!」と申し立てが寄せられる可能性も考えられる、ということです。日本版DBS制度を利用する=いま働いている人に少なくとも特定の性犯罪の前科がある人はいないだろう/日本版DBS制度を利用しない=何かしら表にできない事情があるのではないか、という「根拠のない憶測」を、呼び起こしかねないと運営支援は危惧しています。
運営支援は、「地域に根差した児童クラブ、とりわけ保護者が運営していたり、保護者が運営に関わっていたりする非営利法人の児童クラブは、できる限り、日本版DBS制度を実施する選択をしてほしい」と考えます。日本版DBS制度は、児童クラブに関する限りはとても過酷な制度で、以下に紹介するように導入において実務上、大変な困難を伴います。この制度導入に関して求められる種々の仕組みは、事業運営をする事業者がそれなりに整った法人や団体や自治体であることを当然の大前提としているとしか運営支援には思えず、事業経営のプロフェッショナルではない保護者たちが事業を営む事業形態をまるで考慮していないとすら運営支援には受け取れます。それでも、児童クラブ側はできる限りこの制度を受け入れることを考えていく必要があると運営支援は考えます。
それは、「日本版DBS制度の対応なら万全です。大丈夫ですよ」という、広域展開事業者にさらなる市場拡大の余地、絶好のビジネスチャンスを自動的にもたらすからです。もしも、地域に根差しているクラブで、こどもと保護者の意見を存分に反映させられる児童クラブの存続を願うなら、日本版DBS制度を実施していないことは事業体として法制度の対応に(見た目は)隙が無い広域展開事業者との比較において絶対的に不利になります。そりゃそうですよ。自治体がどの事業者に児童クラブを任せるかとなったとき、日本版DBS制度をしている事業者としていない事業者なら、している事業者を当然に選びます。そもそも、公募型プロポーザルや指定管理者選定における参加の前提条件をクリアできなくなる可能性だって今後は生じるでしょう。
それでも「どうしても日本版DBS制度は無理」というクラブは、運営に関する補助金を将来的に受けられなくなる可能性も念頭にした事業計画を策定しましょう。
<日本版DBS制度を受け入れるとしたら、やるべきことは無数にある>
児童クラブが日本版DBS制度を受け入れることを目指す、つまり「認定事業者」になることを目指すためには、次に記したアからカまでの内容を遂行することが条件になります。「中間とりまとめ」47ページ以降に紹介されています。
ア 犯罪事実確認を適切に実施するための体制の整備
イ 児童対象性暴力等が行われるおそれがないかどうかを早期に把握するための措置の実施
ウ 児童等が容易に相談を行うことができるようにするために必要な措置の実施
エ 児童対象性暴力等対処規程の作成
オ 教育保育等従事者への研修受講
カ 情報管理措置の実施
これは現実的に、地域に根差した小さな児童クラブ運営事業者が完全に遂行するのは非常に困難です。わたくし(萩原)の体感的には、運営する児童クラブが50支援の単位ぐらいに達して本部運営又は事務局機能が充実(少なくとも専従職員が数人いて、かつ、運営最高責任者など役員数名が常駐している)している事業者でないと、予算面でも人的資源においても、完全な対応は難しいと思われます。
しかし、日本版DBS制度を受け入れるならやらねばなりません。このア~カへの対応を含め、とりわけ保護者(出身者)が運営するクラブは独力で日本版DBS制度を受け入れるための対応をこなすのは保母、無理でしょう。まずは「日本版DBS制度を勉強している」弁護士に相談することを運営支援はお勧めします。なかなかそういう専門家が見つからない場合は「日本版DBS制度をしっかり勉強している」社会保険労務士と行政書士に、相談してください。
上記の「ア」だけでも、実に膨大な内容が含まれます。例えば「犯罪事実確認を計画的かつ適切に実施するための業務を管理すること」とあります。しかも極めて重要なのは「責任者」を選んでおくことが求められることです。「ア」について中間とりまとめ49ページに書かれていることを問題なく実施できる場合だとしても、それは児童クラブは認定事業者になる膨大な条件のうちたった1つをクリアしただけです。
また「エ」では、児童対象性暴力等対処規程の作成が挙げられています。これは法律的な考え方ができる専門家が加わらないと作成は難しいでしょう。アとエについては後日、内閣府令やガイドラインによって考え方が整理されることになっていますが、それを見たところで、法律的な思考ができる専門家でないとこの対処規程の作成は難しいでしょう。
つまり児童クラブが日本版DBS制度の対応を目指すには、「法律的な専門家」を今すぐに探しておいて近いうちに業務を依頼することを伝えて受諾してもらっておく必要があります。先にも記しましたが、法律のプロフェッショナルである弁護士さんも全員が全員、日本版DBS制度(こども性暴力防止法)に詳しかったり興味関心があったりするわけでありません。それでも法律家の弁護士であればすぐに対応はできるのでしょうが、これが弁護士ほどの法律的な知識や法的思考を課されていない社労士や行政書士では、日本版DBS制度を興味関心を持って勉強、研究しているかどうかが、依頼先を選択する際の重要な判断基準になります。また、国家資格によっては得意分野があります。日本版DBS制度においては、認定事業者になるための申請手続きが難解です。必要な書類も多岐にわたるでしょう。行政官庁に提出する書類については行政書士が大いに頼みになります。また、下記に触れますが、この日本版DBS制度については労働関係で事前に決まりを作っておく必要があり、それには社労士の力を大いに頼ることができるでしょう。児童クラブ事業者は外部の専門家の力を借りて、日本版DBS制度の受け入れを目指してください。
もちろん、専門家に無料で依頼することはできません。それなりに費用が必要ですからその予算を確保する必要もあります(これが、小さな児童クラブでは対応が難しい理由の1つでもあります)。予算を支払ったのにそれが日本版DBS制度に詳しくない弁護士や社労士、行政書士に依頼したならそれは無駄遣いです。
やらねばならないことは実に多すぎます。今すぐに考え始めてほしいことを下に記します。
・認定申請、手続き=行政書士の力を借りましょう
・安全確保措置の確立=弁護士の力を借りましょう。また、児童精神科医の助言も重要です。具体的な措置の内容について作り上げる際は専門の心理職が策定チームに加わることが運営支援は必要だと考えます。
・犯罪事実確認を児童クラブ事業者が行う際の手続き=GビズIDなど行政書士の支援を求めましょう
・安全確保措置のうち、児童クラブで特に難しいと思われる、「児童対象性暴力等が行われる「おそれがあると認めるとき」の解釈」について=弁護士に相談しましょう
→これは、小学生ともなれば一定の効果を目指して事実とは異なる申出や訴えをする可能性をも考慮すると必要な対応でもあります。もっとも、最重要なのは「性暴力の被害を受け続けていてもなかなか訴えることができないこどもからのSOSサイン、つまり「おそれ」をいかにして見逃さないか」に重点が置かれるべきと運営支援は考えます。
<「就業規則」類の見直し、改正は今すぐにでも着手を>
児童対象性暴力等が行われる「おそれ」に応じた防止措置の内容は、労働法制などを踏まえた事業者内ルール(就業規則等)の策定が必要になります。これは今すぐにでも、弁護士、社労士に相談しましょう。なぜかといえば、児童性暴力等が行われる「おそれ」に関した職員への対応は、事前に就業規則等に作成されていない場合、対応が困難になる可能性が極めて高くなるからです。
中間とりまとめの171ページ以降に説明があります。この部分、非常に厄介なのは中間とりまとめ自身が「事案ごとの措置の有効性は、最終的には司法判断となる」と記していることです。それだけ、訴訟リスクが高い分野であるという認識が必要です。どういうことかといえば、児童クラブの場合、こどもと関わらない職場は極めて限定的で、例えば運営本部や事務局が無い事業者では、こどもと関わらない職場は無し、と言えるでしょうが、仮に、現職者(すでに勤務している人)が日本版DBS制度の定める特定の性犯罪の前科があった場合に、事業者は配置転換などを考えることになります。配置転換しなくてもいいのですが万が一その結果、新たな性暴力被害が生じたら事業者は致命的な過失責任を負うので、まず間違いなく配置転換を考えざるをえないのですが、他にこどもと関わらない職場はなかった場合、では解雇しますか? 解雇しないで給料だけを支払うことはできるかといえば児童クラブ事業者は予算が常に足りないのでそれも困難。ここで極めて難しい局面に陥ります。普通解雇に踏み切った場合、解雇された側が解雇無効を求めて裁判になることが十分にあり得る、ということです。まして、過去の特定の性犯罪の前科が極めて軽いものでその後は社会人としてつつましく生活し勤務態度も極めて優れている職員を配置転換もしくは解雇するなどして裁判にまでもつれたら、裁判の結果はどうなるかおおよそ見当が付きます。
それだけ難しい問題が、他にこどもと関わらない職場がなかなか見つからない児童クラブの日本版DBS制度にはつきまといます。こと、労務管理の点で日本版DBS制度は児童クラブとはきわめて相性が悪い制度です。今回は触れませんが児童クラブで常に必要な夏季休業期間中の短期間のアルバイトを採用するにしても厳重な犯罪事実確認が必要など、人手不足をさらに悪化させる手続きを求める制度になっています。話はそれますが、こども食堂で定期的に学習支援を行っているスタッフも中間とりまとめにおいて日本版DBS制度の対象内に入るとなったとのこと。認定事業者にならねば良いといえばそれまでですが、この制度、「木を見て森を見ず」の制度になりつつあるのではないかとい思い始めています。
慢性的に人手不足に苦しんでいる児童クラブの世界には、過去に残念な事実を起こした人が再起を目指して過去をしっかり隠していれば、再就職先として入り込むだけの余地がありました。それがゆえに、児童クラブの世界の危機感は他の業界に負けることなく強く、それがこの日本版DBS制度の導入を後押しもしました。わたくし自身もDBS制度の有効性には大いに期待したいのですが、こと、日本版DBS制度の児童クラブとの不適合の具合がどうにもはなはだしい、とりわけ地域に根差した児童クラブだけが追いつめられる事態をなんとかして防ぎたい。一方で、どんな人においても基本的人権を守り抜くことが必要という考えからも、過去の過ちは過ちとして、新たな就職先でまっとうに生きている前科のある人を追いつめるだけの結果にならないようにする必要があると考えます。そもそも性暴力は初犯の者が大半。日本版DBS制度の柱は前科確認と並んで性暴力を抑止するための教育研修ですから、再犯はもちろん初犯を起こさないための徹底した教育研修の制度を、児童クラブの事業者は講じなければなりません。ここの対応については児童クラブの事業者は、法律の専門家や労働問題の専門家と十分に相談して、事業者として有効な施策を構築してほしいと期待します。
なお、2026年度から働き始める者の新規採用がすでに進んでいる児童クラブ事業者があるかもしれません。内定者が仮に特定の性犯罪の前科がある場合、内定取り消しをする可能性に迫られますが、それをするにも、事業者側のルールが定められていることが必要です。「重大な経歴詐称がある場合は内定を取り消せる」という趣旨の決まりを事業者が定めておくことが重要です。
つまり、日本版DBS制度の対応は実はもう、とっくに必要となっているのです。中間とりまとめ171ページから181ページに書かれていることを理解し、すぐにでも就業規則類の改正、また就業規則類が無い事業者は新規作成することが、児童クラブの世界には必要です。社労士にすぐ相談してください。就業規則の作成はそう簡単にはできません。その事業者がどのように職員、従業員を処遇しているか、どういう職業人生を過ごしてほしいかの理念を盛り込まないと就業規則は作成できないのです。費用も社労士に依頼すると10万円前後と高額ですが、それは事業者の事業運営に対する理念が込められているのが就業規則だからであって、すぐに簡単に作成できないからなのです。日本版DBS制度に対応した事業者内のルール作りは、今すぐに着手しても遅くはありません。むしろ遅くなりつつあるともいえます。
さて中間とりまとめでは、防犯カメラの有効性を認めた内容にまとめられました(113ページ)。防犯カメラに関するルールや具体的な運用方法のとりまとめ、また設置費用の確保に関する方策を取りまとめる必要があります。(防犯カメラ等について=・性暴力等の発生の抑止力となること ・異常の早期検知が容易になること ・性暴力等の疑いが生じた場合の事実確認が適切に行われ、児童等・従事者の双方をトラブルから守ること)
<最後に一言>
中間とりまとめ4ページに「本年7月には、このような議論を踏まえた施行事項の論点と対応案をまとめた「中間とりまとめ素案」をまとめた。「中間とりまとめ」は、この「中間とりまとめ素案」について、こどもの意見聴取や関係団体等からのヒアリングを踏まえて修正し、制度の骨格を示すものとしてとりまとめるものである。」と記載されています。
つまり関係団体のヒアリングは中間とりまとめに至るまでに一定の効果を果たせる手段であったということです。児童クラブに関するところ、中間とりまとめ素案と、中間とりまとめに関しては変化はなかったと私には思えましたが、児童クラブに関して日本版DBS制度は極めて大企業、広域展開事業者に有利な制度に(それは企図したことではなく結果的にそうなっただけでしょうが)なっていることを少しでも修正できた可能性を、児童クラブの世界の側がみすみす見逃して利用しなかったことは、痛恨の出来事であったと考える次第です。
(お知らせ)
<社会保険労務士事務所を開設しました!>
2025年9月1日付で、わたくし萩原が社会保険労務士となり、同日に「あい和社会保険労務士事務所」を開業しました。放課後児童クラブ(学童保育所)を中心に中小企業の労務サポートを主に手掛けて参ります。なお、放課後児童クラブ(学童保育所)に関して、労働関係の法令や労務管理に関すること、事業に関わるリスクマネジメント、生産性向上に関すること、そしていわゆる日本版DBS制度に関しては、「あい和社会保険労務士事務所」を窓口にして相談や業務の依頼をお受けいたします。「あい和社会保険労務士事務所」HP(https://aiwagakudou.com/aiwa-sr-office/)内の「問い合わせフォーム」から、ご連絡のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
☆
「一般社団法人あい和学童クラブ運営法人」は、引き続き、放課後児童クラブ(学童保育所)の一般的なお困りごとや相談ごとを承ります。児童クラブの有識者として相談したいこと、話を聞いてほしいことがございましたら、「あい和学童クラブ運営法人」の問い合わせフォームからご連絡ください。子育て支援と児童クラブ・学童保育の運営者の方、そして行政の子育て支援と児童クラブ・学童保育担当者の方、議員の方々、ぜひとも子どもたちの安全と安心を守る場所づくりのために、一緒に考えていきましょう。セミナー、勉強会の講師にぜひお声がけください。個別の事業者運営の支援、フォローも可能です、ぜひご相談ください。
☆
(ここまで、このブログをお読みいただきありがとうございました。少しでも共感できる部分がありましたら、ツイッターで萩原和也のフォローをお願いします。フェイスブックのあい和学童クラブ運営法人のページのフォロワーになっていただけますと、この上ない幸いです。よろしくお願いいたします。ご意見ご感想も、お問合せフォームからお寄せください。出典が明記されていれば引用は自由になさってください。)